こんにちは。この記事では、「障害受容」について、筆者自身の体験をもとにお話しします。
障がいを持って生きる中での違和感や悩み、ぶつかった言葉、そして気づいたこと──。
完璧に受け入れられなくても大丈夫。そんな思いを込めて書きました。
- 1. 小さな違和感から始まった
- 2. “治してください”と願った日
- 3. “なんで自分だけ”って、思いたくなった
- 4. 受け入れたふりで、心を守ってた
- 5. 「働けなかったら、施設に行くしかない」──あの言葉の裏にあったもの
- 6. 「できない」より「できること」を数えた
- 7. 受容って、「完全に受け入れる」ことじゃないと思う
- 8. 自分の経験が、誰かの力になると信じて
- 9. あなたに伝えたいこと
1. 小さな違和感から始まった
2. “治してください”と願った日
3. “なんで自分だけ”って、思いたくなった
4. 受け入れたふりで、心を守ってた
5. 「働けなかったら、施設に行くしかない」──あの言葉の裏にあったもの
6. 「できない」より「できること」を数えた
7. 受容って、「完全に受け入れる」ことじゃないと思う
8. 自分の経験が、誰かの力になると信じて
9. あなたに伝えたいこと
1. 小さな違和感から始まった
「なんで、ぼくの足はこんなに言うことをきかないんだろう?」
2歳の頃から、ぼくはずっとリハビリ施設に通っていました。訓練室が日常で、体を動かすことが「遊び」になるような毎日。
そして、小学校に上がるときに進んだのは、地元の小学校ではなく特別支援学校でした。ここでひとつ伝えておきたいのは、特別支援学校が悪いということでは決してないということです。むしろ、先生たちのサポートは手厚くて、一人ひとりに寄り添ってくれる環境がありました。
ただ、当時のぼくは「ほかの子とは違う道を歩んでるんだな」って、自然と感じるようになっていった。“特別”という言葉は、優しさもあるけど、ちょっとした線引きでもある。
だからこそ思うのは、支援学校も、地域の学校も、フリースクールも、どんな進路も選べる社会であってほしいということ。「その子に合った場所を、自分で選べる」──そんな当たり前が、もっと広がっていくといいなと思います。
2. “治してください”と願った日
5歳のある日、自宅に宗教の勧誘の人がやってきました。母と玄関で話すその人は、こう言いました。
「息子さんに障害があってかわいそうですね。神様を信じれば救われますよ」
そう言って、冊子を差し出しました。
その言葉を聞いたとき、ぼくは思わずこう言ってしまいました。「治してください」って。
その女性は何も言わずにぼくを見つめ、母は小さな声で「帰ってください」とだけ言いました。ドアが閉まる音とともに、玄関の空気がふっと冷たくなった気がしました。
しばらくして、母がぼくを抱きしめながら言いました。「ごめんね」
その「ごめんね」には、たぶんいろんな想いが込められていました。励ましたいけどどうしようもない気持ち。治してあげたいのに治せない現実。
その日を境に、「障害が治るかもしれない」という希望は、ぼくの中でそっと幕を閉じました。
3. “なんで自分だけ”って、思いたくなった
特別支援学校に通う中で、「違い」はあたりまえのように存在していました。みんなそれぞれ、得意なことや苦手なことがあって、それが前提の環境。だからこそ、“できないこと”に対して誰かから責められることはなかったし、「なんでできないの?」なんて問いかけを受けた記憶も、正直ありません。
でも、自分の中ではずっと、「できないことへの悔しさ」がくすぶっていました。その気持ちがいちばん強くなるのは、双子の兄と一緒にいるときでした。
同じ日に生まれたのに、同じように育ってきたのに、兄は走れるし、何でもひとりでできる。ぼくにはできないことが、兄には当たり前のようにできる。その“違い”を、毎日のように目の当たりにするのは、想像以上にしんどいことでした。
一番近くにいる存在だからこそ、「なんで自分だけ…」という気持ちは、心の奥に強く残り続けたんです。
4. 受け入れたふりで、心を守ってた
中学生になるころには、車椅子生活が日常になっていました。「障害がある自分」というのも、頭では理解していたし、大人からは「ちゃんと受け入れててえらいね」と言われることもありました。
でも、実は違ってた。受け入れてる“ふり”をしていただけだった。そうしないと、心がもたなかったから。
高校に入ってからは、周囲とどんどん差がついていった。バイト、旅行、恋愛……。「自分だけ置いていかれてる」気がして、そっと距離をとるようになった。
5. 「働けなかったら、施設に行くしかない」──あの言葉の裏にあったもの
高校3年の進路指導のとき、先生に言われた言葉は、今でも忘れられません。
「働けなかったら、施設に行くしかないよ」
「大学に行けなかったら、施設に入るしかないんだから」
その瞬間は、衝撃でした。“障害がある”ってだけで、可能性を閉ざされるような気がして、悔しくて、胸がギュッと締めつけられた。
でも不思議と、涙は出ませんでした。代わりに、燃えるような気持ちが湧いてきたんです。
「そんなわけあるか。見とけよ、絶対やってやる」って。
今思えば、あの先生は、ぼくの“負けん気の強さ”をちゃんと見抜いてたんだと思います。あえてあんな言葉をぶつけてきたのは、きっと、ぼくの心に火をつけるためだったんじゃないかって。
その一言がなければ、ぼくは今ほど「できることを探してみよう」なんて思えなかったかもしれない。傷ついたけど、同時に前へ進むきっかけになった。あれは、叱咤激励だったんだって、今なら思えるんです。
6. 「できない」より「できること」を数えた
そこから、ぼくの視点は変わりました。“できないこと”じゃなく、“できること”に目を向ける。
絵は苦手。でも、人の話を聴くのは好き。走れない。でも、文章を書くのは好き。手先は不器用。でも、人の気持ちには敏感かもしれない。
小さな「得意」や「好き」をひとつずつ書き出してみたら、胸の奥がじんわりしてきました。
「何もない」なんて思ってたけど、気づいてなかっただけだったんだ。
7. 受容って、「完全に受け入れる」ことじゃないと思う
あらためて思う。障害受容って、なに?
「障害を前向きに受け入れてる姿」は美しく語られるけど、実際は、揺れる日も落ち込む日もあって当然。
ぼくも、今でもときどき「やっぱりしんどいな」と思う日がある。でも、そういう気持ちもふくめて、全部“自分”だと思えたとき、ちょっと楽になれた。
8. 自分の経験が、誰かの力になると信じて
大学では福祉を学び、自分の経験を話す機会も増えました。最初は緊張したけど、誰かが「共感しました」「救われました」と言ってくれるたび、「この体でも、生きる意味はあるんだ」って思えるようになった。
あのとき「施設に行くしかない」と言われた自分に、いまならこう言える。
「そんなことない。あなたは、ちゃんと社会の一員だよ」
9. あなたに伝えたいこと
今、これを読んでくれているあなたが、障害を受け入れられなくて苦しんでいるのなら──
無理に受け入れなくても大丈夫。泣いたり怒ったり迷ったりするのが、ふつうなんです。
ぼく自身、今だって完璧じゃないし、「やっぱり健常だったら…」と思う日もある。でも、それでも生きてる。今日も笑って、ごはんを食べて、大切な人と話せたら、それで十分。
障害受容は、終わりのない旅路。でも、その道を歩くあなたを、ぼくは全力で応援しています。

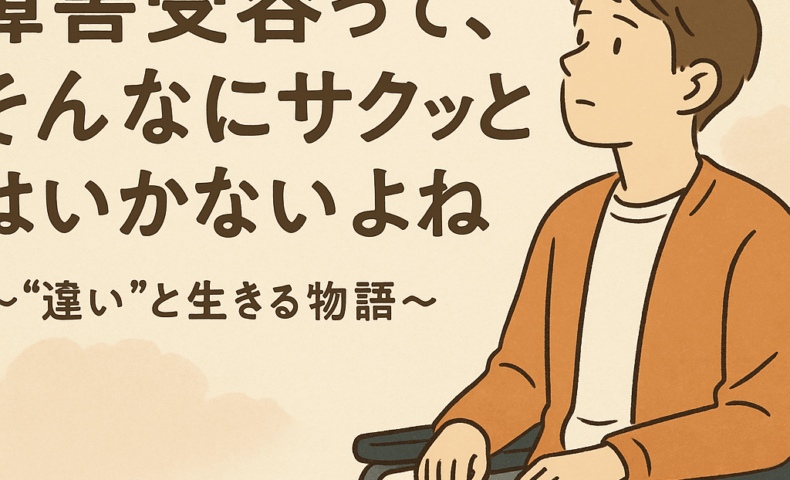
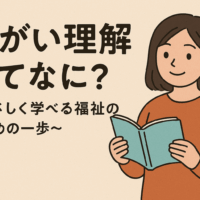
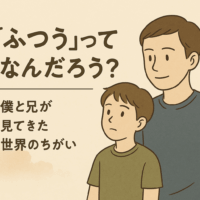
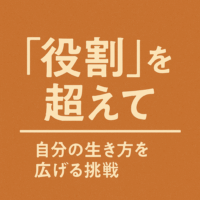

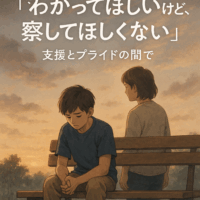
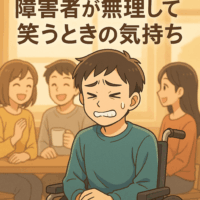
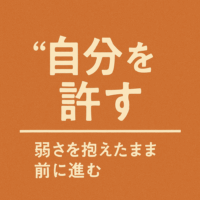


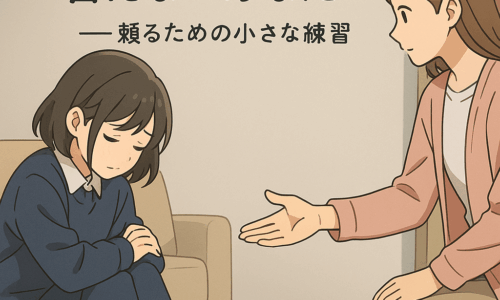
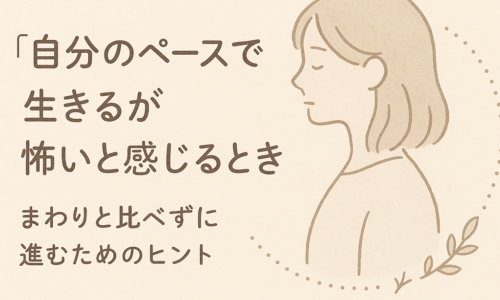


この記事へのコメントはありません。