「配慮してほしい」と「特別扱いされたくない」のあいだ
障害当事者として生きていると、こんな気持ちになることがあります。「困っているときには助けてほしい、でも特別扱いはされたくない」。この記事では、その“微妙なバランス”に揺れる気持ちを丁寧に言葉にしていきます。
助けを求めたときの“視線”がつらい
困っている場面で支援をお願いしたとき、まわりから「偉いね」「優遇されてる」といった視線を感じることがあります。障害支援の頼み方に正解はありませんが、“配慮”と“特別視”は全く違うものだということを理解してほしいのです。
「がんばっててえらい」は本当に励まし?
明るく生活しているだけで「すごいね」と言われることがあります。でもそれは、障害があるから評価されているという感覚につながることも。私たちが求めているのは、“普通に接してもらえること”だったりします。
対等でいたいからこそ、頼るのが難しい
配慮を受ければ「特別扱い」と思われる、かといって我慢すれば生活に支障が出る。そんな間で、何度も揺れてきました。だからこそ、自分から「これは配慮であり、特別ではない」と伝える工夫も必要だと感じています。
配慮とは“支配”ではなく“尊重”であること
障害者への配慮とは、可哀想だから助けるのではなく、「あなたのやり方を尊重します」という意思表示です。その違いを理解してもらえるかどうかで、障害当事者の安心感は大きく変わります。
「してあげる」は上下関係を生む
配慮が“上から目線”に感じられると、感謝よりも「申し訳なさ」が先に来てしまうことがあります。対等な関係での支援には、「どうしたらやりやすいですか?」という“相談”の姿勢が重要です。
支援は「共有する行動」としてのコミュニケーション
困っている人を支えることは、“一方的な援助”ではなく“協力”です。「この場面では手伝ってもらえると助かる」と伝えることができれば、支援は自然なやり取りになります。障害者コミュニケーションの伝え方の基本は、相互の理解と確認にあります。
「配慮」と「特別扱い」の違いを伝える力
例えば、「エレベーターの使用」は必要な配慮。でも「先にどうぞ」といつも優先されるのは、時に“特別感”を感じることもあります。必要なときに必要な支援を受けられる環境こそが、本当のバリアフリーです。
なぜ「気づかれない配慮」が理想なのか
当事者の気持ちとしては、「配慮を受けている」と周囲に意識されない形が一番心地よいときがあります。さりげないサポートが、自分の尊厳を守ってくれるのです。
「やってあげた感」がない支援は心地よい
支援する側が“特別なことをしている”と強調しない関係のほうが、お互いにとって自然体になれます。必要なときに、必要なことだけ、静かに手を貸す――それが理想的な配慮です。
「言われないとわからない」ことは悪くない
誰もが最初から配慮できるわけではありません。当事者が「こうしてもらえると助かります」と伝えることで、相手も学ぶ機会になります。“察する”ではなく“聞く”ことで、コミュニケーションは成長します。
「ありがとう」と言いやすい支援とは
お互いが無理をしていない関係では、感謝の言葉も自然と出てきます。形式的な「ありがとう」ではなく、「ほんとうに助かった」という実感のこもった言葉が、心の距離を縮めていくのです。
“配慮されすぎること”が生む孤独
配慮が過剰になると、「気をつかわれている」「距離を置かれている」と感じることもあります。障害当事者の気持ちとしては、「もっと自然に関わってほしい」という願いがあります。
「配慮=近づかない」が一番さみしい
「話しかけたら迷惑かも」「触れたらいけない話題かも」――そんな遠慮が、関係性を遠ざけてしまうことがあります。配慮とは“避けること”ではなく、“関わるための工夫”なのです。
支援よりも“対話”がほしかった瞬間
困っているとき、手を差し伸べてもらうことももちろんありがたい。でも何より嬉しかったのは、「最近どう?」と何気なく声をかけてくれる人の存在でした。会話のなかにある配慮は、心をつなぎます。
「対等な配慮」があたりまえになる社会へ
障害があるから、特別に配慮されるのではなく、一人ひとりの違いに合わせて“あたりまえに調整される社会”。それが、目指すべき未来です。誰もが「わざわざ」ではなく、「自然に」支え合える関係へ。
配慮と対等性は、両立できる
障害のある私たちが本当に望んでいるのは、「特別な扱い」ではなく「自然な関わり」です。自立と支援、配慮と対等性は、どちらか一方を選ぶものではありません。バランスの中にこそ、本当の共生があります。
「できること」と「頼ること」は両立できる
自分にできることは自分でやる。だけど、難しいことは素直にお願いする。そのスタンスがあれば、支援も配慮も自然なものになります。頼ることは“負け”ではなく、“選択”なのです。
障害のある人が「主導権」を持つという視点
支援を受ける側に主導権があると、「やられる」ではなく「選ぶ」感覚になります。配慮もまた、当事者がどう受け取りたいかに重きを置いてこそ意味を持ちます。
「ふつうに関わること」の価値
結局のところ、一番ありがたいのは「ふつうに接してくれること」です。障害の有無にかかわらず、相手に興味を持ち、気持ちを尊重し合える関係が、社会を温かくしてくれます。

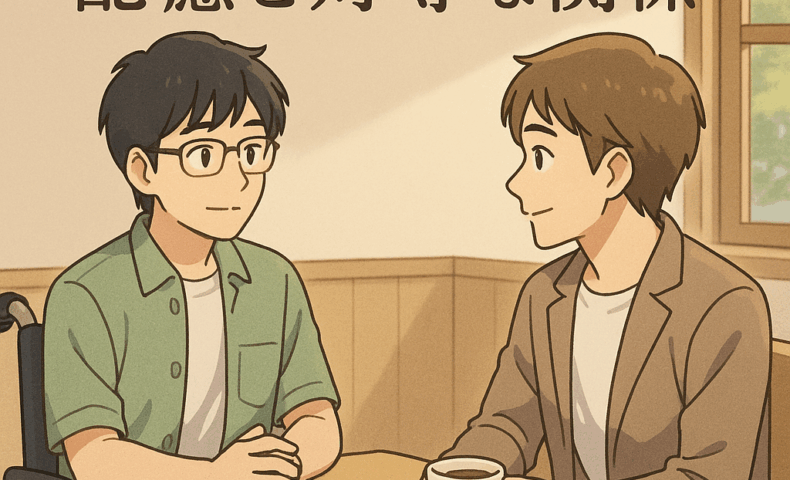
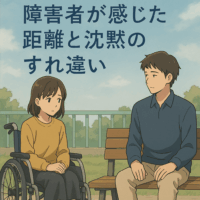


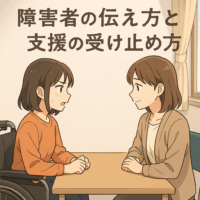
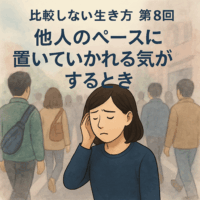
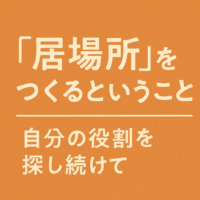



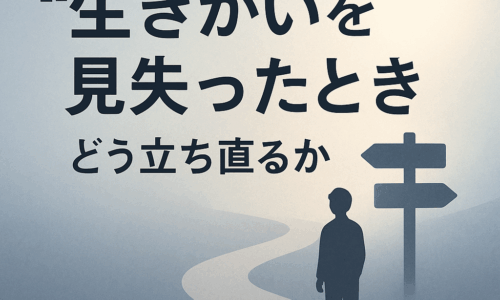


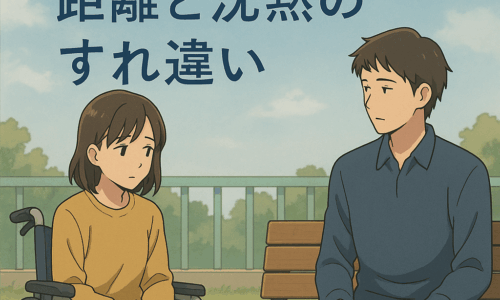
この記事へのコメントはありません。