リード文:
「これはできません」と言うことは、今でも少し勇気がいります。
でも、できないことを正直に伝えたうえで、「これならできます」と差し出すことで、
支援は一方的なものから“やりとり”へと変わっていきました。
“お願いする”ことを学んだあと、今度は“できること”をどう活かすか――
その気づきと実践について、等身大の思いで綴ります。
目次
- 1. はじめに ── できないことを隠さないって、こわいけど自由だ
- 2. 「ごめんね、できないんだ」から始まる関係
- 3. 「できない」を伝えることは、相手への思いやりでもある
- 4. 「できないこと」に引け目を感じていた頃
- 5. 交換するように支え合う ― “支援のキャッチボール”
- 6. 支援されることと、役割を持つことのあいだで
- 7. まとめ ― できないままでも、つながれる世界へ
1. はじめに ── できないことを隠さないって、こわいけど自由だ
「これはできません」
そう言うことって、正直、ずっと苦手でした。
できないって言ったら、がっかりされるんじゃないか。
迷惑に思われるんじゃないか。頼りないって思われるんじゃないか。
そんなふうに思ってしまって、できないこともつい「がんばります」って言ってしまうことが、私にはよくありました。
でも最近、少しずつ変わってきた気がします。
「できないことを認める」って、実はすごく誠実なことで、
“できること”をちゃんと差し出す準備ができているってことなんだと、思えるようになったんです。
2. 「ごめんね、できないんだ」から始まる関係
あるとき、仲間と共同で何かに取り組む場面がありました。
私は段取りを考えたり、全体の流れを組み立てたりするのは得意なんですが、
細かな作業――たとえばファイリングのような手先を使う作業は、どうしても時間がかかってしまいます。
だから、チームで動くときは、そういった作業をお願いして、代わりに全体の進行役やまとめ役を引き受けるようにしています。
私が得意なのは、人の話をじっくり聞くことや、内容を要約して文書を作成すること、そして福祉制度に関する知識を活かして情報を整理することです。
「そこはできないんだけど、記録をとることならできるよ」と伝えたら、
「ありがとう。そうしてくれたら助かる!」と笑ってもらえたんです。
できないことを伝えたのに、感謝された。
それがすごくうれしくて、気がついたんです。
“できること”を差し出すって、ただの作業じゃなくて、信頼のやりとりなんだって。
3. 「できない」を伝えることは、相手への思いやりでもある
昔の私は、「できないって言うのは申し訳ないこと」と思っていました。
でも今は少し考えが変わってきました。
「できます」と言ってやりきれなくなったり、途中で誰かに迷惑をかけてしまったりするよりも、
最初から正直に「ここはできない」と伝える方が、お互いにとっても安心できるし、信頼が生まれやすいと思うようになったんです。
そして何より、できないことを隠さないって、自分にもやさしい。
背伸びしてがんばるよりも、「私はこれが得意です」と差し出すことの方が、ずっと自然で、ずっと力強い。
今の私は、「これはできません。でも、これならできます」と、そんなふうに言える人でありたいと思っています。
4. 「できないこと」に引け目を感じていた頃
「自分にできないことを伝える」というのは、頭でわかっていても、やっぱり勇気がいります。
特に以前の私は、「これをお願いしてしまったら嫌な顔をされるかもしれない」とか、
「できない自分って、申し訳ない存在なんじゃないか」って、そんなふうに考えてしまうクセがありました。
手伝ってほしいのに言えなかったり、できないことを、つい「がんばればできる」とごまかしてしまったり――。
本当は、自分が無理をしていることに、誰よりも自分が気づいていたのに。
5. 交換するように支え合う ― “支援のキャッチボール”
でも、あるとき気づいたことがあります。
できないことを認めるって、そこで終わりじゃないんです。
「でも、私にはこういう力があります」って、自分の“できる”を差し出すことで、
まるでキャッチボールのように、お互いが支え合える関係が生まれるんだと。
私は段取りを整えるのが得意です。
人の話を聞いて、必要な情報をまとめたり、文書にまとめたりするのも得意です。
福祉制度にも詳しいから、知らない人にわかりやすく説明することもできます。
その一方で、ファイリングなどの細かい作業には時間がかかるので、そういったところは他の人にお願いして、
私は全体の調整や記録を引き受ける、そんな形で関われるようになりました。
できない部分を補ってもらって、できる部分で返していく。
一方的な“支援”ではなく、自然な“役割のやりとり”が生まれていったのです。
6. 支援されることと、役割を持つことのあいだで
「支援される側だから」と、何もできないわけじゃない。
たとえできないことがあっても、自分の役割や得意を活かせる場面はきっとある。
そして、そうした“できること”が周囲に伝わっていくと、「お願いされる側」にもなることが増えていきます。
あるときは、文章チェックを頼まれたり、あるときは、「この制度について教えて」と聞かれたり。
“お願いすること”と“お願いされること”が交互にやってくる中で、
私は少しずつ「支援される側」という一面的な立場から、「支援の一部になれる存在」として、関わっていけるようになった気がします。
熊谷晋一郎さんの言葉が、ここでも深く響きます。
「自立とは、依存先を増やすこと」
私にとっての自立とは、「なんでも一人でやること」ではなくて、
できないことはお願いして、できることは気持ちよく差し出すこと。
その繰り返しの中で、信頼と安心の輪が広がっていく――
それが、今の私にとっての“自立”のかたちです。
7. まとめ ― できないままでも、つながれる世界へ
今でも私は、完璧ではありません。
お願いすることに戸惑う瞬間もあるし、「これでいいのかな」と不安になることもあります。
でも、「これはできません」と伝えられるようになったこと、
「でも、こういうことでなら力になれます」と差し出せるようになったことは、
私が私らしく生きるための、大きな一歩だったと思っています。
できないことがあるのは、あたりまえ。
でも、だからこそ、できることが誰かの役に立つ。
そんなふうに支え合える社会であってほしいし、私自身も、そうしたつながりをつくる一人でありたいと願っています。
“できない”を認めて、“できる”を差し出す。
それはきっと、特別なことじゃなくて、誰にとっても自然な「関わり方」のひとつなんだと思います。
だからこそ私は、資格を取得したり、日々学びを続けたりしながら、支援や業務をより良くする方法や効率化についても考えています。
自分のできることを精いっぱいやることが、自分自身の役割をつくり出し、社会の中で果たしていける力になると感じています。

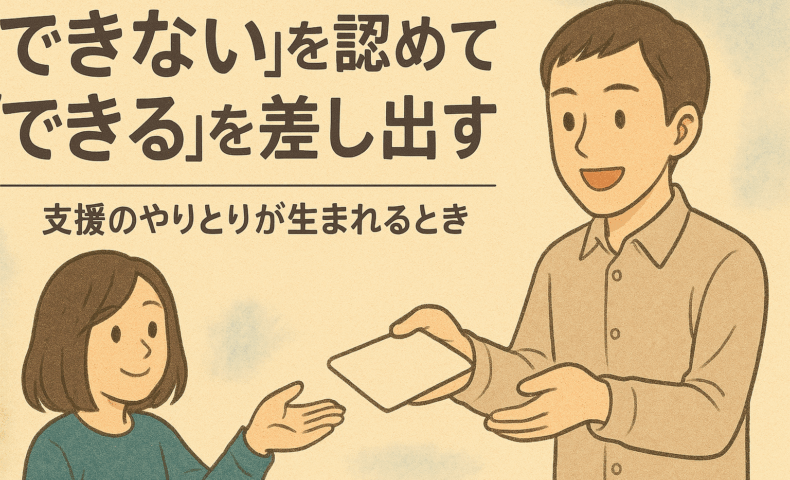


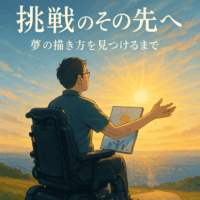
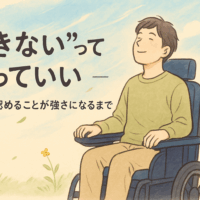

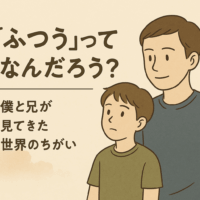





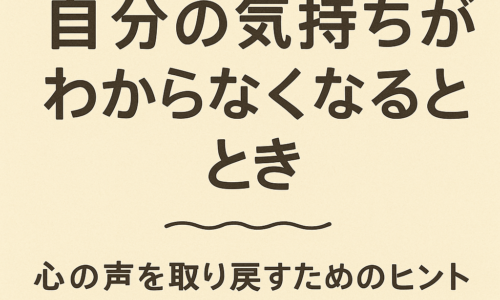

この記事へのコメントはありません。