目次
- 1. ドアの向こうにできた境界線
- 2. “治してください”と願った幼い日の記憶
- 3. “違い”が日常だった特別支援学校で
- 4. 受け入れたふりで心を守っていた日々
- 5. 「施設に行くしかない」と言われた進路指導
- 6. “できないこと”より“できること”を探した
- 7. 障害受容は、終わりのない旅
- 8. 東京で出会った“自然な声かけ”
- 9. 共に生きるってどういうこと?
- 10. 最後に ― やさしさは、誰かの生きやすさになる
1. ドアの向こうにできた境界線
中学1年の春、兄に「お前、出てくんなよ。友達来るからさ」と言われた。言葉が返せず、ただ「そっか…」と呟いて、部屋のドアを閉めた。この日、僕たちの間に見えない“境界線”ができた気がした。
2. “治してください”と願った幼い日の記憶
5歳の頃、宗教の勧誘に「障害があってかわいそう」と言われ、「治してください」と思わず口にした。母は静かに「帰ってください」と言い、僕を抱きしめて「ごめんね」と言った。あの日を境に、“治るかもしれない”という希望は静かに消えた。
3. “違い”が日常だった特別支援学校で
特別支援学校では、みんながそれぞれのペースで生きていた。「できないこと」を責められることもなかった。でも、双子の兄と過ごす時間には、“できない悔しさ”が静かに積もっていった。兄はできて、僕はできない。毎日その現実を突きつけられていた。
4. 受け入れたふりで心を守っていた日々
中学から高校にかけて、「障害のある自分」を受け入れている“ふり”をしていた。本当はしんどかったけど、受け入れたふりをしないと心がもたなかった。周囲ができていく中、自分だけが置いていかれるようで、距離を取っていった。
5. 「施設に行くしかない」と言われた進路指導
高校3年の進路相談で、「大学に行けなかったら施設に行くしかない」と言われた。衝撃だった。でも、その言葉が「絶対やってやる」というエネルギーになった。今思えば先生は、僕の負けん気を信じて、わざとあえて言ったのかもしれない。
6. “できないこと”より“できること”を探した
自分にできることは何かを探し始めた。絵は苦手だけど、文章を書くのは好き。手先は不器用だけど、人の話を聞くのは得意。小さな“できること”を見つけていくうちに、自信が育っていった。
7. 障害受容は、終わりのない旅
障害受容とは、“完全に受け入れること”ではない。落ち込む日も、羨ましいと思う日もある。でも、そんな自分を否定しないこと。揺れながらも「これも自分」と思えるようになったとき、少しだけ楽になった。
8. 東京で出会った“自然な声かけ”
一人で東京に行ったとき、駅で「エレベーターの場所わかりづらいのでご案内しますよ」と女性に声をかけられた。過剰でもなく無関心でもない、“自然なやさしさ”がうれしかった。
9. 共に生きるってどういうこと?
支える/支えられるという一方通行じゃなく、お互いの“できること”を持ち寄ること。それが共生の第一歩。僕は誰かの役に立てるし、誰かの支えにもなれる。その循環があれば、“違い”は分断ではなく、つながりのきっかけになる。
10. 最後に ― やさしさは、誰かの生きやすさになる
過去の経験があったからこそ、やさしさの意味を知ることができた。やさしさは、特別なスキルじゃない。ただ少し想像して、一歩寄り添ってくれること。それがどれだけ救いになるか、僕は何度も実感してきた。
あなたの何気ない行動が、誰かの“生きやすさ”になるかもしれない。今日のやさしさが、明日の希望になることを願って。

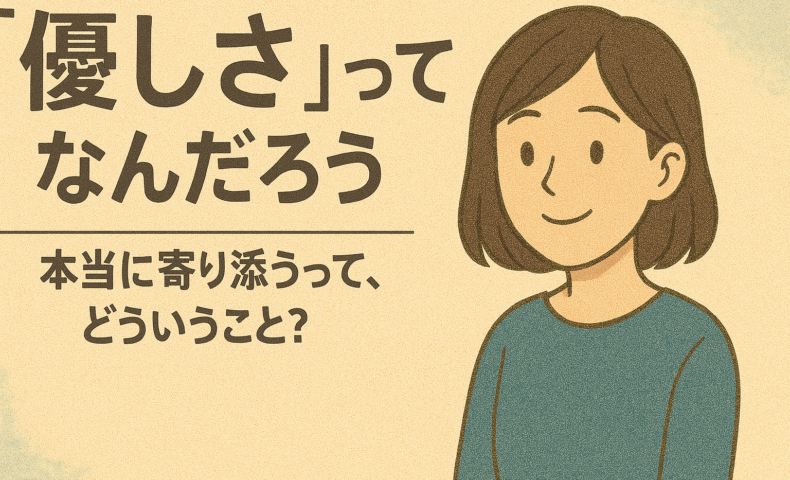




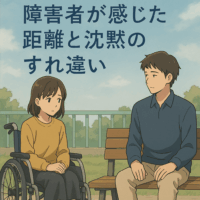



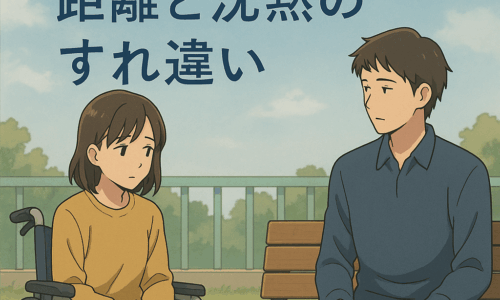




この記事へのコメントはありません。