目次
- 1. はじめに ── 「隠してたつもりはないけど、話せなかった」
- 2. 「できるだけ目立たないようにしていた」学生時代
- 3. 「カミングアウトじゃなくて、会話として」伝えるということ
- 4. 自分から話すことで生まれた“対等なつながり”
- 5. 「名刺1枚」が、私を変えた
- 6. 隠さないことで、私が少し強くなれた
- 7. まとめ ── 見せることでつながった世界
1. はじめに ── 「隠してたつもりはないけど、話せなかった」
「自分の障害について、どう向き合ってますか?」
そう聞かれたら、昔の私はたぶん、「うーん、隠してるつもりはないんですけどね……」って答えていたと思います。
たしかに、私は電動車椅子に乗っていて、見た目で“障害がある”ことはすぐわかる。
でも、それでも――「自分のことをちゃんと話す」って、実はずっとできていませんでした。
「脳性麻痺です」「右手が少し動きやすいです」「こういうサポートがあると助かります」
そうやって、堂々と話せるようになるまでは、ずいぶん時間がかかりました。
「障害を隠さない」って、見た目だけじゃなくて、“自分から言葉にすること”なんじゃないか。
そんなことを考えるようになったのは、少しだけ、自分に自信が持てるようになってからでした。
2. 「できるだけ目立たないようにしていた」学生時代
私が学生だった頃、なるべく「普通」に見えるように、意識していた気がします。
友達と話すとき、授業を受けるとき、ちょっとでも「手伝おうか?」って言われたら、「大丈夫!」って即答していた。
本当は、教科書を開けるのがちょっとだけ大変だったり、プリントを配るタイミングに間に合わなかったり、そんなことがしょっちゅうだったのに。
“頼ったら負け”みたいな空気を、自分の中で勝手につくってたんですよね。
「障害があるからできない」って思われたくなかったし、「すごいね」って言われるのも、ちょっと違う気がしてたし、何より、「かわいそう」と思われるのが怖かった。
だから私は、いつも「頑張ってる人」でいようとしてました。
でもそれって、“自分を見せないようにしてる”ってことだったんですよね。
3. 「カミングアウトじゃなくて、会話として」伝えるということ
社会人になってしばらくして、ある研修会で出会った人に、こう言われたことがあります。
「最初に“障害があります”って言ってくれて、すごく助かりました。どう接したらいいか迷わずに済んだので。」
そのとき、ちょっと驚いたんです。
自分としては、そんなつもりで話したわけじゃなかった。ただ、仕事の話をするときに「私は電動車椅子を使っていて、こういう支援があれば助かります」と説明しただけ。
でもその人にとっては、それが壁を取っ払う一言だったらしい。
そのとき思ったんです。
「障害を隠さない」って、“カミングアウト”みたいに重たく考える必要ないのかも。
ただ、「こういう自分です」って、話の流れの中で、自然に共有すること。
それだけで、相手との関係性がちょっとだけ柔らかくなる。
それ以来、私は無理のない範囲で、自分のことを“話す”ようになりました。
4. 自分から話すことで生まれた“対等なつながり”
私は、高校まで特別支援学校に通っていたので、「障害を隠している」という感覚はあまりありませんでした。周りも全員、何かしらの支援を受けながら過ごしていて、そこでは“見せる”も“隠す”も、あまり意味をなさなかったのかもしれません。
でも、普通高校との交流があったとき、ふと自分の中にある「よく見せたい」という気持ちに気づきました。
「大丈夫です」「できますよ」本当は少し不安があったとしても、そう答えていた自分がいました。
たぶん、「健常者に近づきたい」という気持ちがあったんだと思います。「頼らない自分」でいたかった。「特別扱いされない自分」でいたかった。
そんな私が、障害を“隠さずに話す”ようになったきっかけがあります。
それは、特別支援学校から県外の大学に一人で進学したことでした。
5. 「名刺1枚」が、私を変えた
大学に入学したとき、私は孤独でした。知り合いもいない、土地勘もない。そして何より、自分ひとりでは生活がままならないことも多い環境。
先輩から聞いていたのは、「できないことをうまく伝えられなくて、誰にも頼れず中退した」という障害学生の話。
そんな話を聞いた私は、決めていました。最初に、ちゃんと“伝える”ことをしよう。
そこで、私は自作の「名刺」を作りました。
名前と連絡先だけじゃなく、「できないこと」「手伝ってもらえたら助かること」も書きました。たとえば:
- 電動車椅子の操作のこと
- 段差がある場所の移動のこと
- 書類の記入や、教室の場所の確認など
この名刺を、履修登録の列で隣にいた人に配りはじめました。「はじめまして!こういうことがあるので、もし困ってたら気軽に助けてもらえたら嬉しいです」って。
それがきっかけで、少しずつ友達が増えていきました。
ある日、友達のひとりがこう言ってくれました。
「最初、どう関わっていいか分からなかったけど、話しかけてくれて本当にほっとした」
その言葉を聞いたとき、私は初めて、“障害を見せる”って、相手の不安も和らげることなんだと気づいたんです。
6. 隠さないことで、私が少し強くなれた
「見せる」って、怖いことです。弱さをさらけ出すみたいで、誤解されたらどうしようって不安にもなります。
でも私は、名刺を配りながら、伝えながら、少しずつ「そのままの自分」を受け入れられるようになっていきました。
「できないこと」を知っても、離れていく人は少なかった。むしろ、「教えてくれてありがとう」と言ってくれる人がほとんどでした。
隠さないことで得られたのは、対等な関係と、ちゃんとした“信頼”でした。
もし、あのときの自分が無理して「大丈夫、大丈夫」と繰り返していたら、もしかしたら今の自分はいなかったかもしれません。
「助けてほしい」と言えることは、「弱さ」ではなくて、“一歩踏み出す強さ”なんだと、今では思えます。
7. まとめ ── 見せることでつながった世界
「障害を隠さない」って、大げさなカミングアウトじゃなくていいと思うんです。
ただ、自分から「こういうことがあるんだよ」と話せるかどうか。相手にどう思われるかよりも、どうやって“つながっていくか”を考えること。
私は、自分の障害について話せるようになってから、関係の幅が広がりました。
助けてもらえることも増えたし、何より「自分が無理をしなくていい」という安心感がありました。
だから今、誰かに聞かれたらこう言います。
「障害を隠さないって、“生きやすくする工夫”でもあるんですよ」
それは、自分のことをきちんと伝えようとした過去の自分が、少しずつ教えてくれた答えです。

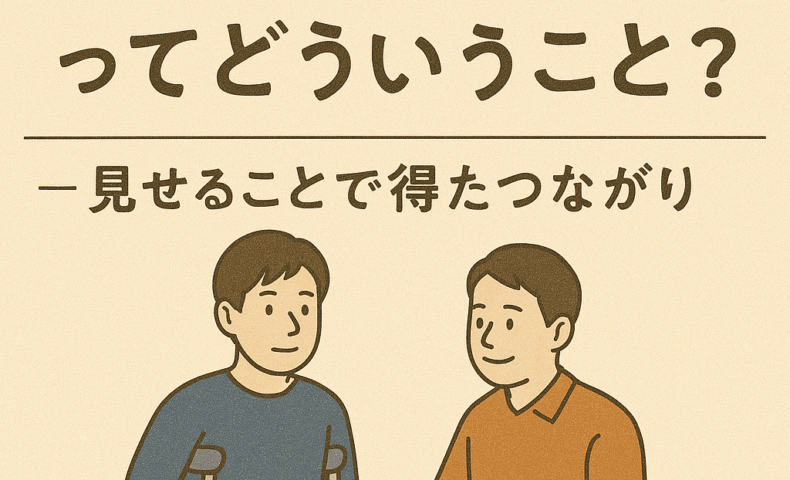
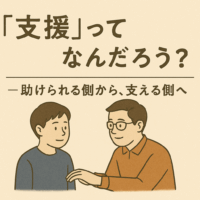
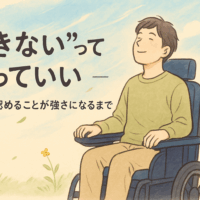






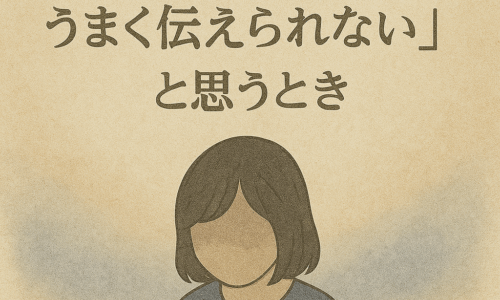
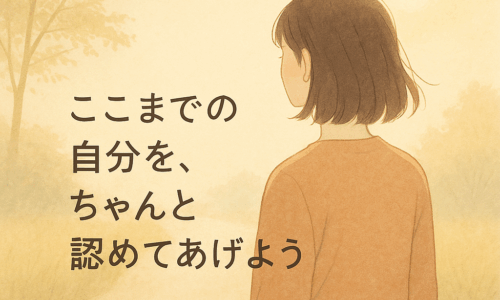
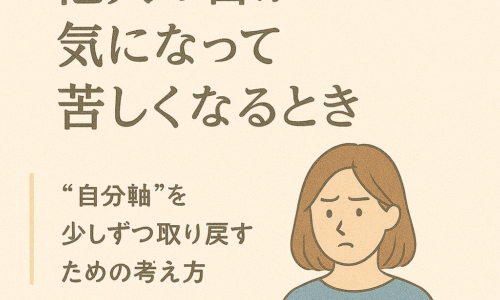
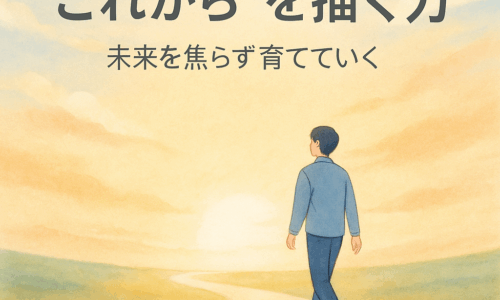
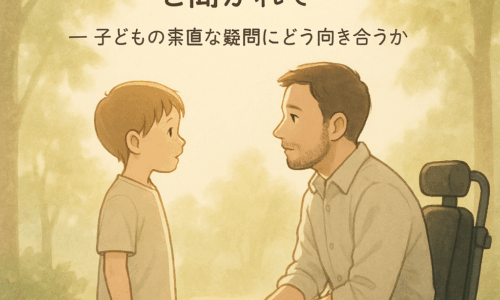
この記事へのコメントはありません。