「何かあったら言ってね」「困ったら手伝うよ」
その言葉が、優しさだとわかっていても、どこかで引っかかってしまう自分がいた。
――“察してほしい”わけじゃない。でも、“わかってほしい”という気持ちは、確かにある。
支援が必要な場面と、ひとりで頑張りたい気持ち。その狭間でゆれる「プライド」と「弱さ」。
今回は、そんな私自身の経験をもとに、“支援される”ということについて、正直に綴ってみたいと思います。
- 支援って、ありがたい。でも…
- “言わなくても察してほしい”と思ってしまう自分
- プライドと弱さのあいだで
- 自分で伝える勇気 ― それでも「お願いする」
- 支援者としての気づき ― 相手のプライドを守る支援とは
- 最後に ― わかってほしい、でも、決めつけないでほしい
1. 支援って、ありがたい。でも…
支援はありがたい。
それは、間違いなく本音です。
でも同時に、こうも思うのです。
「いつも助けられてばかりじゃダメなんじゃないか」「またお願いしたら、頼りないと思われるんじゃないか」と。
私には、脳性麻痺という障害があります。
電動車椅子を使い、日々生活しています。
例えば、駅の改札でタッチパネルが高すぎて届かないとき。
誰かが気づいて声をかけてくれると助かる。でも、それが“いつも”になると、申し訳なさや情けなさも同時に湧いてくる。
2. “言わなくても察してほしい”と思ってしまう自分
本当は、「手伝ってください」と言えればいい。
でも、言うことで「できない人」と思われたくない気持ちがある。
そんなとき、つい思ってしまうんです。
――“察してくれたらいいのに”って。
でも、これって、すごく勝手な期待かもしれません。
だって、誰だって他人の事情や気持ちを完璧に読み取ることなんてできないから。
それでも、言葉にしづらいことほど、「察してほしい」という願いが強くなる自分がいます。
3. プライドと弱さのあいだで
自分の中にあるプライド。それは、「障害があってもできることを増やしたい」という思いでもありました。
でも、どんなに努力しても、できないことはある。
だから、助けを求める。それもまた、自分を守る手段の一つだと知ったのは、時間が経ってからでした。
「強く見られたい」と思ってしまうのは、弱さを隠したいから。
でも本当の強さって、自分の弱さを受け入れて、それを伝えられることなんじゃないかと、今は思います。
4. 自分で伝える勇気 ― それでも「お願いする」
大学に進学して、名刺を作って自分の苦手なことを最初に伝えるようになってから、少しずつ「お願いする」ことに抵抗が減っていきました。
できないことを隠さない。そのことで、相手も安心して関われる。
お願いすることで、相手との信頼関係が築ける。
それを知ってから、「察してほしい」という気持ちよりも、「伝える努力をしよう」という気持ちが少しずつ勝るようになりました。
5. 支援者としての気づき ― 相手のプライドを守る支援とは
私は今、放課後等デイサービスの管理者として、障害のある子どもたちと関わっています。
その中で気づいたのは、「支援」は「手伝うこと」だけではないということ。
相手が「できた」と感じられるようにサポートすることが大事なんです。
例えば、手伝う前に「やり方はどうしたい?」と聞くこと。
「自分でやってみる?」と選択肢を渡すこと。
支援者の立場になった今だからこそ思います。
相手のプライドを守る支援こそが、本当の意味での「わかろうとする姿勢」なんだと。
6. 最後に ― わかってほしい、でも、決めつけないでほしい
「わかってほしい」
それは、“障害があるから大変なんだろうな”と勝手に決めつけられることじゃなくて、
“どう関わってほしいか”を一緒に考えてくれること。
「察してほしくない」
それは、思い込みで先回りされて、できることまで奪われたくないという願い。
支援とプライドは、矛盾するようでいて、どちらも大切な人間らしい感情。
だからこそ、お互いが「わかり合おうとする姿勢」を持ち続けることが、何より大切だと思います。
私もこれからも、「伝える努力」と「受け止める姿勢」の両方を大事にしていきたいです。

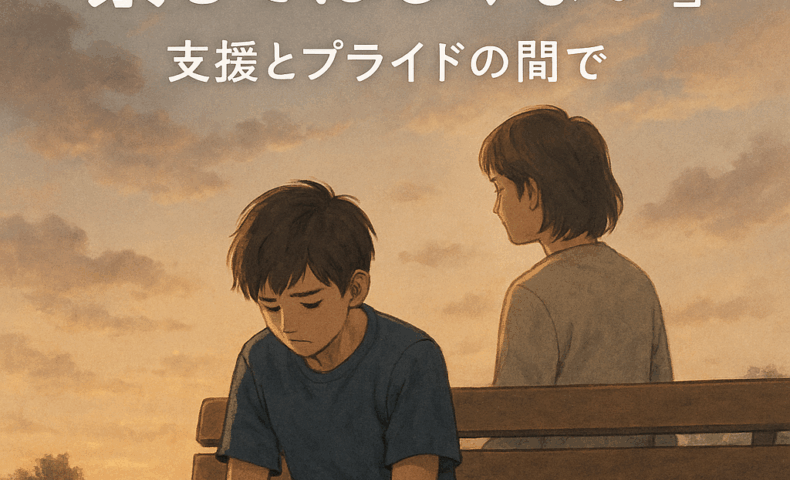
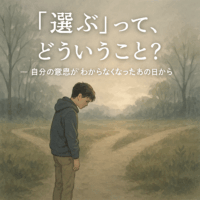
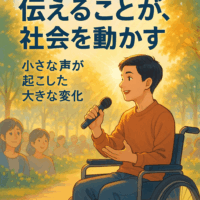

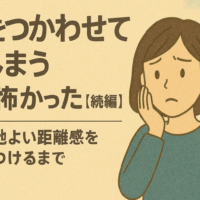

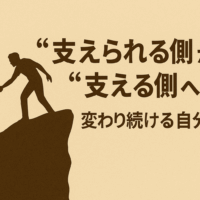

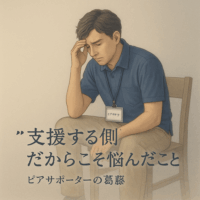
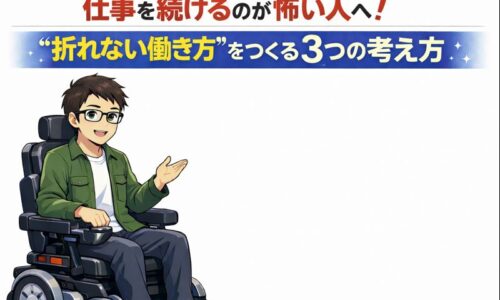
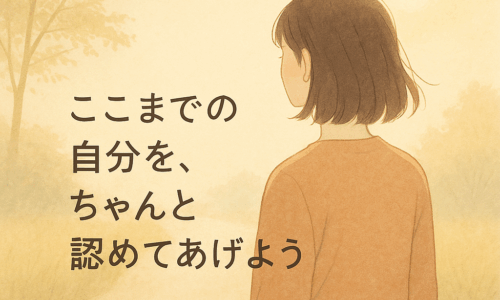
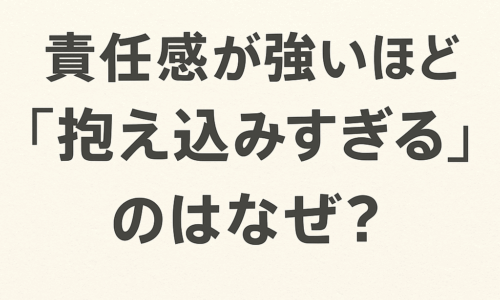
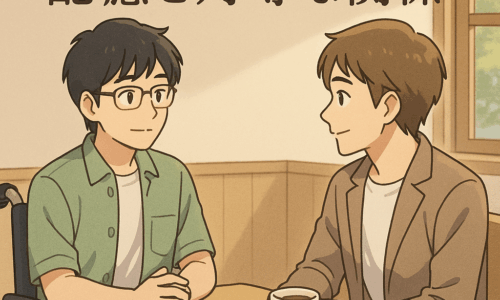

この記事へのコメントはありません。