「わかってほしい」と「察してほしくない」の間で
「障害があることを理解してほしい」と思う一方で、「過剰に気をつかわれるのはしんどい」と感じた経験はありませんか?今回は、当事者として抱えてきたその“間の気持ち”を、言葉にしてみたいと思います。
本当はわかってほしいことがある
電動車椅子で生活していると、「わかってくれてるな」と感じる瞬間が嬉しくなることがあります。でも、それは決して“察して動いてほしい”という意味ではありません。理解されることで孤独感が薄れ、「一人じゃない」と思えるのです。
過剰な気づかいがつらい理由
逆に、なんでも先回りされてしまうと、「自分でできることまで奪われる」と感じることもあります。「障害がある=できない前提」で接されると、力を出すチャンスが減ってしまい、自尊心にも影響します。だから「察されすぎる」のはしんどいのです。
“対等な関係”でいられる距離感
私が理想とするのは、“特別扱い”でも“無関心”でもなく、自然体で向き合える関係です。「手伝おうか?」と一言聞いてくれるだけで、「察し」ではなく「会話」が生まれます。その一歩が、支援と尊重のバランスをとる鍵になるのです。
—
察してもらうことに疲れた日々
「何かあれば声かけてね」――よくある言葉なのに、なぜか気を使ってしまう。頼ることが「空気を読まないこと」になってしまいそうで、つい我慢してしまう。そんな日々の中で感じた葛藤をつづります。
助けてほしいのに、言えなかった
支援が必要なときも、「今は忙しそうだし」「声かけたら迷惑かな」と思って遠慮してしまうことが多くありました。「察してもらえるのを待つ」のは、気づかれなかったときの寂しさと裏返しです。だから余計に、しんどくなっていくのです。
頼る=迷惑という思い込み
「お願いすること=相手の負担になる」という思い込みは、過去の体験や環境から刷り込まれたものでした。けれど本当は、お願いされる側も「頼ってくれた」ことで距離が近くなったと感じることが多い。その視点を得て、少しずつ変わっていきました。
無理しない関係を築くには
支援を求めるとき、「○○してもらえたら嬉しいです」と自分の気持ちを添えて伝えるようにしています。相手の気持ちにも配慮しつつ、自分の思いを伝えることで、負担にならない形で助けを求める関係性が育っていくと感じています。
—
「伝える力」は鍛えられる
察してもらうのをやめて、自分の気持ちを言葉で伝えるようになったのは、大人になってからでした。最初は勇気がいりましたが、「伝える」ことには練習と工夫が必要だと気づき、少しずつ変わっていきました。
名刺をきっかけに伝える
大学入学時に「これが苦手で、これはできます」と書いた名刺を配った経験は、伝える練習の第一歩でした。無理に“察してもらう”のではなく、先に“伝える”ことで関係性がスムーズになったのです。ツールに頼るのも立派な方法の一つです。
場面に応じた伝え方を持つ
家族、友人、職場…それぞれの場面で伝え方は違います。フランクに言える関係もあれば、丁寧に説明が必要な関係もあります。だからこそ「自分のパターン」を持つことが、安心して過ごすための鍵になります。
失敗しても、次に活かせばいい
うまく伝えられなかったこともたくさんありました。でも、「こう言えばよかったかな」と振り返ることで、少しずつ“自分なりの伝え方”ができてきました。完璧じゃなくていい、伝えることは“更新”していくものなのです。
—
“察し”に頼らないコミュニケーション
「気づいてくれたら嬉しいけど、それが前提になるとしんどい」――そう感じる当事者は少なくありません。だからこそ、“察し”に頼らず、“ことば”で築く関係性をめざして、実践していることがあります。
「聞いてくれてありがとう」を忘れずに
どんな些細なことでも、話を聞いてもらえたときは「ありがとう」と伝えるようにしています。「話していいんだ」「聞いてもらえるんだ」と思えることは、次につながる自信になります。そしてそれは、相手への信頼も育ててくれます。
説明の途中で遮られたとき
話を最後まで聞いてもらえなかったとき、「察したつもり」で決めつけられたように感じて落ち込むことがありました。「最後まで聞いてもらえること」が、私にとっての“対話”でした。だからこそ、お互いの話を聞き合うことが大切です。
“察するより、聞いてみて”
「どうしたらいい?」と一言聞いてもらえるだけで、「察される」よりずっと心地よい関係が生まれます。「答えは本人の中にある」と信じてくれる人がいることが、当事者にとって大きな安心感になるのです。
—
支援とは、“一緒に考える”こと
支援は“与える”ものでも、“一方的に受ける”ものでもありません。当事者と支援者がそれぞれの視点を持ち寄って、“一緒に考える”ことが、本当の支援につながると私は思っています。
専門性だけでは届かない想い
私は社会福祉士・精神保健福祉士として専門知識を学びました。でも、それだけでは“気持ち”には届かないこともあります。当事者としての経験を通して、「わかる」と「わかろうとする」の違いに気づきました。
問いを持ち続ける姿勢
「どう支援するか」よりも、「どんなふうに一緒に歩めるか」を常に考えています。答えは一つじゃないし、相手によっても変わります。その都度、問い直す姿勢が、関係性を深めてくれると信じています。
支援=役割の交換
支援者と当事者、立場は違っても「できること」「苦手なこと」はお互いにあります。支援とは“上からの手助け”ではなく、“役割の交換”だと思っています。だからこそ、尊重し合う姿勢が、何より大切なのです。

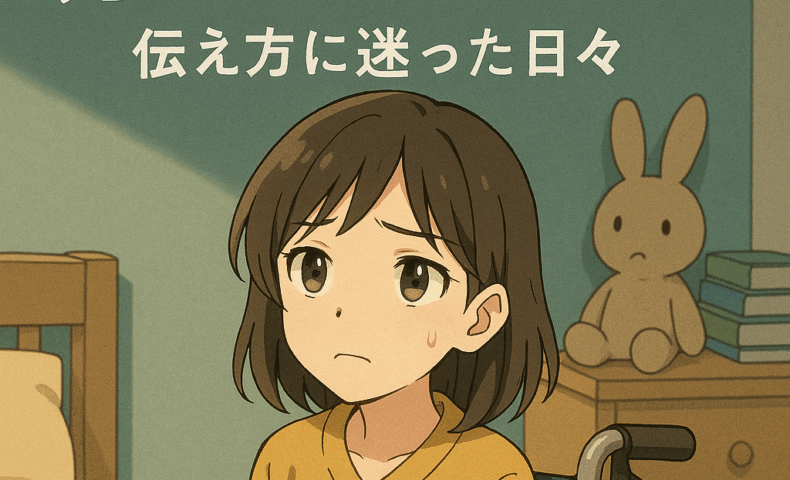
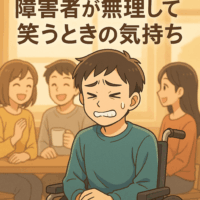



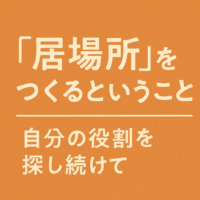
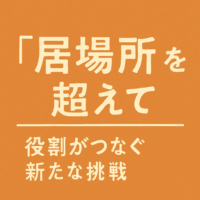
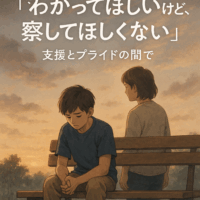
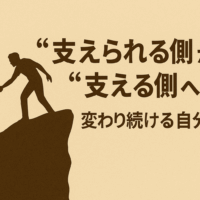
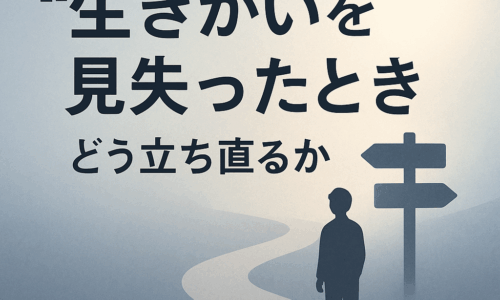
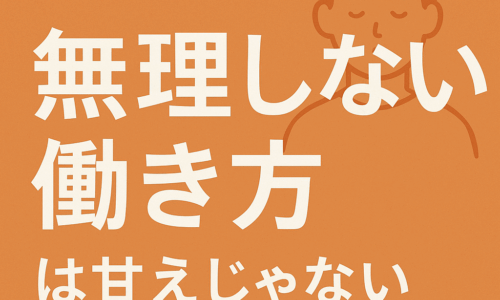
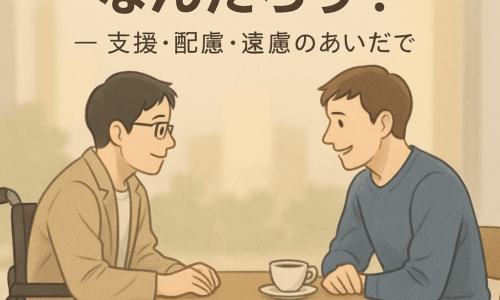
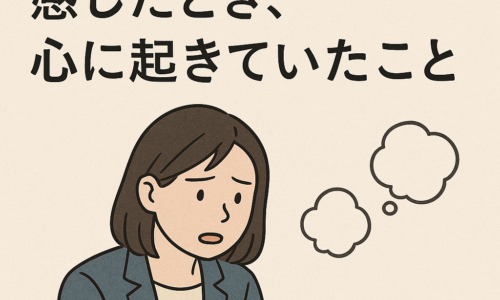
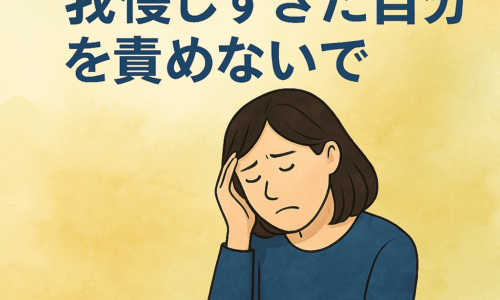
この記事へのコメントはありません。