「普通にして」って、どういう意味?
「もうちょっと普通にしてくれる?」「みんなと同じようにしてね」…そんな言葉を何度も聞いてきました。でも、“普通”ってなんなのでしょうか。多数派の価値観を「正解」とする社会のなかで、違いが生きづらさになる現実を見つめ直してみます。
「違和感」は、私のせいじゃなかった
学校や職場など、人が集まる場面で「なんとなく居心地が悪い」と感じたことはありませんか?私はよくありました。けれど最近になってようやく、「自分が変だから」ではなく、「環境が違いを受け止める設計になっていなかった」と気づいたんです。
“普通”という言葉の曖昧さ
「普通」は人によって基準が違います。でも多くの場合、「多数派のふるまい」が普通とされがちです。障害があると、身体の動かし方や話し方が違うことがありますが、それを“普通じゃない”とするのは、視野が狭い社会の問題かもしれません。
合わせることに疲れた過去
「無理してでも馴染もう」と頑張っていた時期がありました。でも、表情や言葉を作るたびに、自分が薄れていくような感覚がありました。合わせすぎることは、生きるうえでの“呼吸”を奪っていくことだと感じました。
少数派という立場で見えてきたこと
障害があるということは、多数派とは違うニーズや表現方法を持っているということ。だからこそ、そこから見える社会の“形”があると思っています。少数派であるからこそ気づけたことを、ひとつずつ言葉にしてみます。
目立つことへの恐れ
電動車椅子に乗っているだけで目立ちます。注目されるのが怖くて、「人混みを避ける」「声を出さないようにする」など、自分を小さくするような工夫ばかりしていました。でもそれは、“自分が悪いから”ではなかったと、今なら言えます。
当事者だからこその視点
段差やトイレの配置、案内表示のわかりにくさ…健常者には気づかないことが、当事者には見えてしまう。それは苦しさでもあり、同時に社会の改善ポイントを見つける“力”でもあります。この視点は、支援にも制度設計にも活かせる財産です。
少数派であること=弱さではない
「少ない=劣っている」ではありません。むしろ、少数派が声を上げることで、多様性が尊重される社会が育ちます。違いを否定するのではなく、“違いがあることを前提に”社会が動いていくような未来が理想です。
「伝わらない前提」から始める大切さ
違いがあるということは、言わなければ伝わらないことがあるということ。自分の気持ちや考えをきちんと伝えることは、面倒でもあり、勇気のいることでもあります。でもその一歩が、誤解やすれ違いを減らすための鍵になります。
「説明するのが面倒」は本音
「わざわざ自分の状況を説明するのが面倒」そう思うこと、たくさんあります。でも、説明せずに誤解される方が、あとでモヤモヤが残る。だから私は、「最初の一言」を少し頑張って伝えるようにしています。
共感より理解を求めたい
「大変だね」と共感されるより、「何を配慮すればいいか教えて」と言ってもらえる方が、ずっとありがたいです。気持ちに寄り添うのも大切ですが、具体的な行動につながる理解こそ、当事者にとって本当に助かる支援です。
伝えたあとのやり取りが関係を作る
一度伝えたから終わりではなく、その後のコミュニケーションが大切です。「これでよかった?」「次からこうするね」などの声かけがあるだけで、「わかろうとしてくれている」と感じられ、関係性が深まります。
無理に“普通”を目指さなくていい
“普通”を装うことに疲れていた日々が、今の自分の土台になっています。そして今なら、「普通じゃなくても、自分らしくいられる場所はある」と伝えられます。無理に合わせすぎない生き方を、誰もが選べる社会を目指したいです。
“わかってもらえない”から離れる勇気
どれだけ説明しても、分かってもらえないこともあります。そんなときは、「その場から離れる」「わかってくれる人に切り替える」ことも選択肢の一つです。わかってもらう努力は大事ですが、自分を守ることも同じくらい大事です。
ありのままを出せる居場所
肩の力を抜いて過ごせる場所は、私にとって福祉の現場や、同じ当事者の仲間たちとのつながりでした。完璧な理解ではなくても、「そのままでいいよ」と言ってくれる存在があることで、人は安心して自分を出せるようになります。
“違い”を受け入れる社会の育て方
「みんなと同じ」ではなく、「みんな違っても大丈夫」が当たり前になる社会を目指すには、まずは身近なところから対話を始めることです。家族、職場、地域の中で、「違っていいよ」と言える文化を少しずつ育てていきたいと思います。
「あなたのままでいい」と言える社会へ
障害のある私が、“普通”に合わせることをやめてから、ようやく深く呼吸できるようになりました。誰かに合わせるのではなく、自分の輪郭を持って生きていく――そんな生き方ができる社会は、きっと誰にとっても生きやすいはずです。
“正しさ”の押しつけから自由に
「それは普通じゃない」「もっとこうしたほうがいい」といった“正しさ”の押しつけは、ときに人を苦しめます。正解がひとつじゃないことを認め合える文化が、多様性を本当に尊重する土台になるのではないでしょうか。
当事者だからできる発信
障害当事者であるからこそ、「こういう視点もあるよ」と社会に伝えていく役割を持つことができます。自分の言葉で、自分の体験から発信することで、共感や理解の輪が広がっていきます。
「そのままのあなたで大丈夫」と伝えたい
もし今、「普通にならなきゃ」と苦しんでいる人がいたら、こう伝えたいです。あなたは、あなたのままでいい。無理に合わせなくてもいい。違いを力に変えていける社会を、一緒につくっていきましょう。



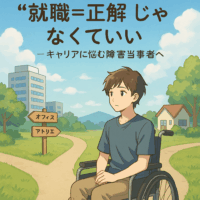


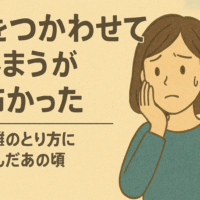


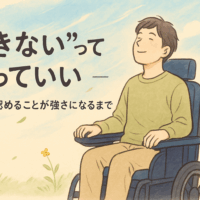

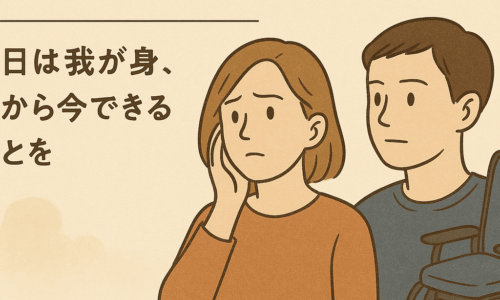



この記事へのコメントはありません。