私たちは、日常の中でどうしても人と比べてしまいます。
学校での成績や、社会に出てからの仕事の成果。暮らしぶりや交友関係、家庭環境や趣味の充実度…。現代社会では比較の材料が溢れています。特にSNSでは、他者の「一番よい瞬間」や「自慢できる部分」だけが切り取られて流れてくるため、どうしても自分の現実と比べて落ち込んでしまいやすいのです。
「どうしてあの人はあんなにうまくやっているんだろう」
「同じ年齢なのに、私の方が遅れている気がする」
「もっと努力しなければ認めてもらえない」
こうした思いは、誰しも一度は抱いたことがあるのではないでしょうか。
■ 私自身も比べやすい性格だった
私自身も、実はとても比べやすい性格です。
さらに承認欲求が強く、「誰かに認めてもらいたい」という気持ちに振り回されることが少なくありません。
特に障害があると、日常生活の中でどうしても他者の支援が必要になります。食事や移動、仕事の場面でも、支えがあることで初めて成り立つことがたくさんあります。そのため、心の奥底に「嫌われたら支援を受けられなくなるかもしれない」という不安が常につきまといます。
その恐怖感が、「もっと頑張らないと」「人から良く思われないと」「迷惑をかけたと思われたら終わりだ」といった強迫観念につながり、必要以上に「他人の評価」を気にしてしまうのです。
障害があると「支援が必要だからこそ、人間関係を大切にしなければ」という気持ちが人一倍強くなる。
でもその一方で「本当はどうしたいのか」という自分の気持ちを置き去りにしてしまうこともあります。
■ 比較も承認欲求も「自然なこと」
ここで大切なのは、比較してしまうことや承認欲求そのものが「悪いものではない」ということです。
比較するからこそ目標ができたり、学びが生まれたりします。
承認欲求があるからこそ努力ができたり、人とつながる喜びを感じられたりもします。
つまり、「比べてしまうのは仕方ないこと」「認められたいと思うのも自然なこと」だとまずは受け止めてあげることが大切なのです。
私自身も、比べて落ち込むことが多々ありますが、最近は「比べてしまう自分も人間らしい」と認められるようになってきました。
■ “頼る”ことを肯定する
もう一つ大事なのは、「人に頼ることを肯定する」という視点です。
日本社会では「自立」がとても重視されます。そのため「自分でできることは自分でやる」「人に迷惑をかけない」という考え方が強く根付いています。
けれども、支え合うことは本来、人間にとって自然なことです。誰しも一人で生きているわけではなく、社会や周囲の人に支えられて生活しています。
障害の有無にかかわらず、助け合いは人間関係の基本。
それなのに、「支援を受ける=迷惑をかける」「頼る=甘え」と思い込んでしまうと、自分をどんどん責めてしまうことになります。
ここで一歩立ち止まって考えたいのは、
「頼ることは弱さではなく、生きる力だ」ということ。
頼ることは、人とのつながりを深める行為であり、支え合いを生み出すきっかけです。
■ 「支援があるからこそできること」がある
私自身、障害があるからこそ「人の支えがあるから生きられている」という実感があります。
電動車椅子がなければ出かけることもできませんし、制度やサービス、そして日々支えてくれる人たちがいなければ、今の仕事や活動も続けられなかったでしょう。
支援があるから「できること」が広がる。
人に頼れるからこそ「自分の力を発揮できる」場が増える。
そう考えると、頼ることは決して後ろめたいことではなく、むしろ「自分らしく生きるための手段」なのだと思えるのです。
■ 「比較に振り回されない」ためにできること
とはいえ、日常で比較に振り回されることはなくなりません。
そんなときに私が意識している工夫を、最後にいくつか共有します。
- 比べて落ち込んだら、「比べてしまうのは人間らしい」とまず認める
- 人からの支援を受けてできたことを「自分の成果」として受け止める
- できなかったことではなく「今日できた小さなこと」に目を向ける
- 信頼できる人に「今の気持ち」を言葉にして伝える
- SNSから一度離れて、自分のペースを取り戻す
特に「小さなできたこと」を見逃さずに積み重ねることが、比較の渦から抜け出すための大きな力になると感じています。
■ まとめ
障害があると、どうしても「頼ること」に後ろめたさを抱いたり、人の評価を過剰に気にしてしまったりします。
けれど、比べてしまうのも承認欲求を持つのも、人間として自然なこと。
そして、支援を受けることは弱さではなく「生きる力」であり、頼ることがあるからこそ私たちは「自分らしく生きられる」のだと思います。
比べて落ち込む自分も、誰かを頼る自分も、すべてをそのまま肯定できたとき、少しずつ「比較に振り回されない生き方」が見えてくるのではないでしょうか。


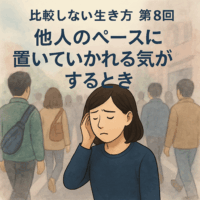


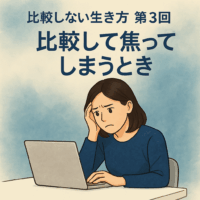
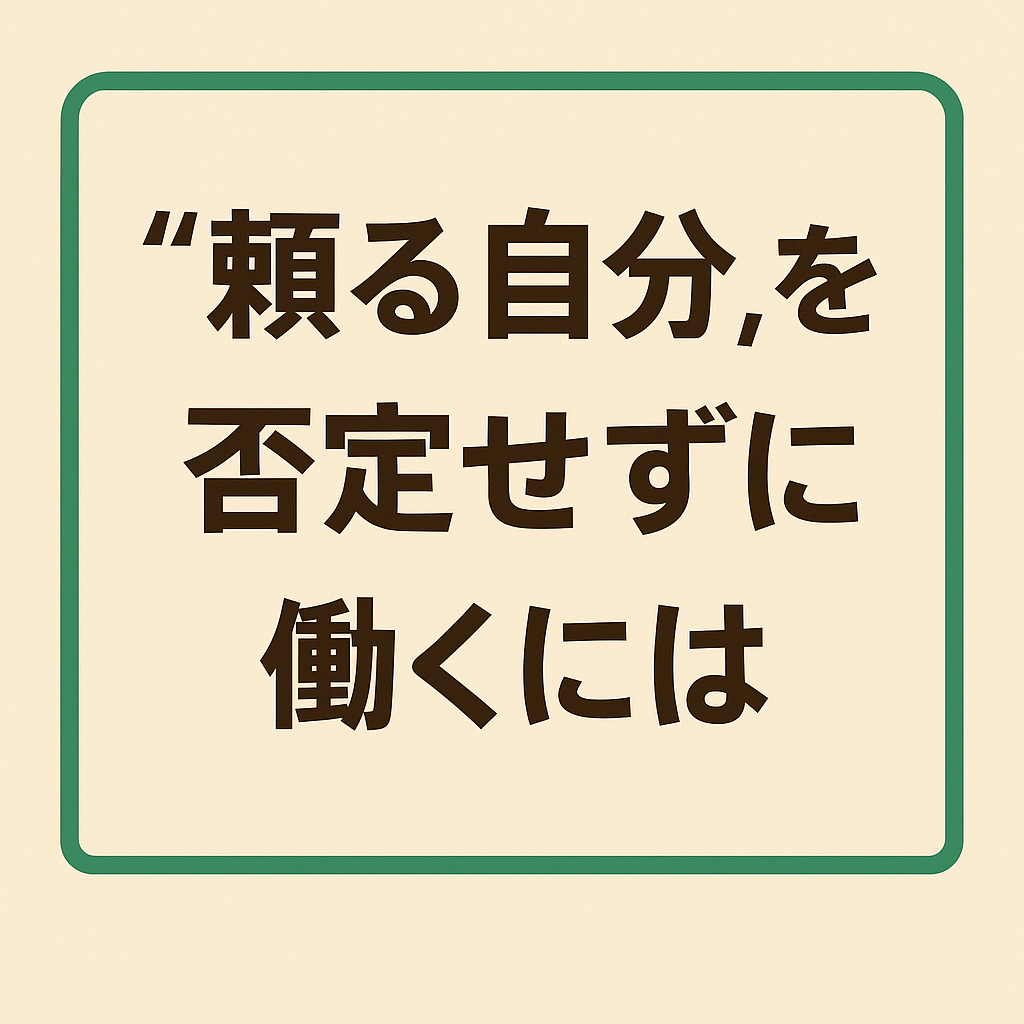
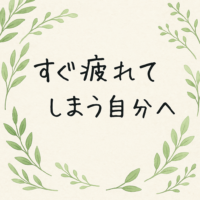
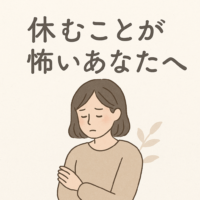

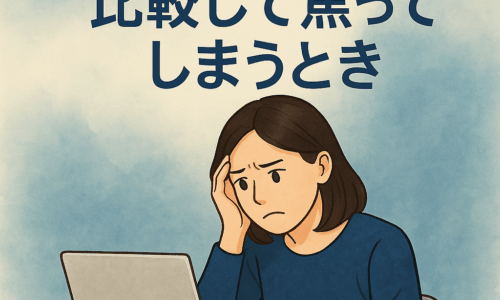
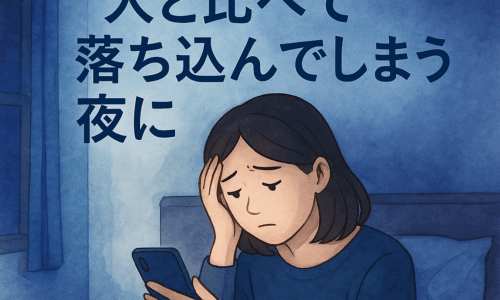


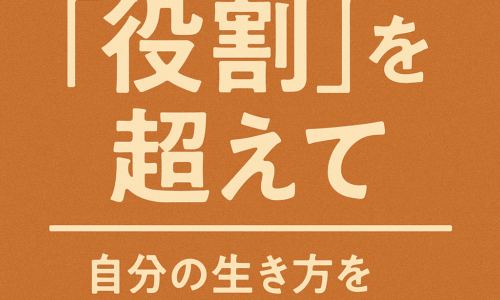
この記事へのコメントはありません。