責任感が強い人が抱え込みやすい理由
「自分がやらなきゃ」
「人に迷惑をかけたくない」
そんな思いを持つ人ほど、仕事や課題を一人で抱え込みやすい傾向があります。
背景にはいくつかの心理的要因があります。
- 評価されたい気持ち
周囲から「頼りになる」と思われたい。 - 完璧主義
人に任せると不安で、「自分でやった方が確実」と思ってしまう。 - 失敗の恐れ
過去に注意された経験から「次は絶対に失敗したくない」と強く思ってしまう。
責任感が強いこと自体は決して悪いことではありません。
しかし、それが「自分一人で背負い込むこと」と結びついてしまうと、働き方や生き方を苦しくさせてしまうのです。
抱え込みがもたらす悪循環
私たちが“抱え込みすぎる”と、次のような悪循環が生まれます。
- 業務の質が落ちる
一人で処理しきれなくなり、細部が雑になったり、期限に間に合わなくなる。 - 心身に不調が出る
残業続きで疲労がたまり、睡眠不足や体調不良を招く。 - 孤立感が強まる
「自分だけ頑張っている」と感じ、チームとのつながりが弱まる。 - さらに責任感が強まる
「迷惑をかけた」と自己否定し、もっと頑張らなきゃと考えてしまう。
こうして、「責任感が強い → 抱え込む → 不調 → もっと抱え込む」というループが生まれてしまうのです。
私自身の体験から
私も、責任感の強さから抱え込みすぎた経験があります。
管理者として現場を任され、「全部自分でやらなければ」と思い込んでいました。
例えば、書類作成、保護者対応、職員調整、研修準備…。
どれも大事な業務ですが、一人で同時に抱え込むには無理がありました。
その結果、睡眠時間を削り、体調を崩し、気づけばミスも増えていました。
結局、周囲に迷惑をかけてしまい、「あの時、もっと早く相談していれば」と悔やんだのです。
その経験から学んだのは、**責任感は「一人で背負う力」ではなく、「共有して成果を目指す力」**だということでした。
責任感を“共有できる力”に変える工夫
では、どうすれば「責任感=抱え込み」にならずに済むのでしょうか。
私が実際に取り入れて効果を感じた工夫を紹介します。
① 「一緒に考えてほしい」と伝える
「助けてください」と言うのは勇気がいります。
そんなときは「一緒に考えてもらえますか?」と相談ベースで話すと、相手も受け入れやすくなります。
② 責任を分け合う仕組みをつくる
役割分担や進捗確認の仕組みをチームで決めておくと、「自分だけで背負わなくていい」という安心感につながります。
③ 小さな相談を重ねる
いきなり大きなことを任せるのは難しいですが、「この資料だけ確認してもらえますか?」といった小さな相談を重ねることで、少しずつ頼れる関係が築かれます。
④ ミスを共有する文化を意識する
「失敗=責任を取らされるもの」ではなく、「チームで改善するもの」と考える。
そういう意識を持つことで、責任を一人で抱え込まなくてよくなります。
まとめ ― 責任感は「ひとりで背負う」ことではない
責任感は大切な力です。
けれど、それを「全部自分でやらなきゃ」と思い込むと、抱え込みすぎて自分も周囲も苦しくなります。
本当の意味での責任感とは、**「成果をみんなで達成するために動く力」**です。
だからこそ、一人で抱え込むのではなく、共有し、頼り合いながら進めることが大切なのです。
無理に強い自分を演じなくても大丈夫。
責任感を「抱え込む力」ではなく「分かち合う力」に変えることで、より自分らしく、そして安心して働けるようになるのだと思います。

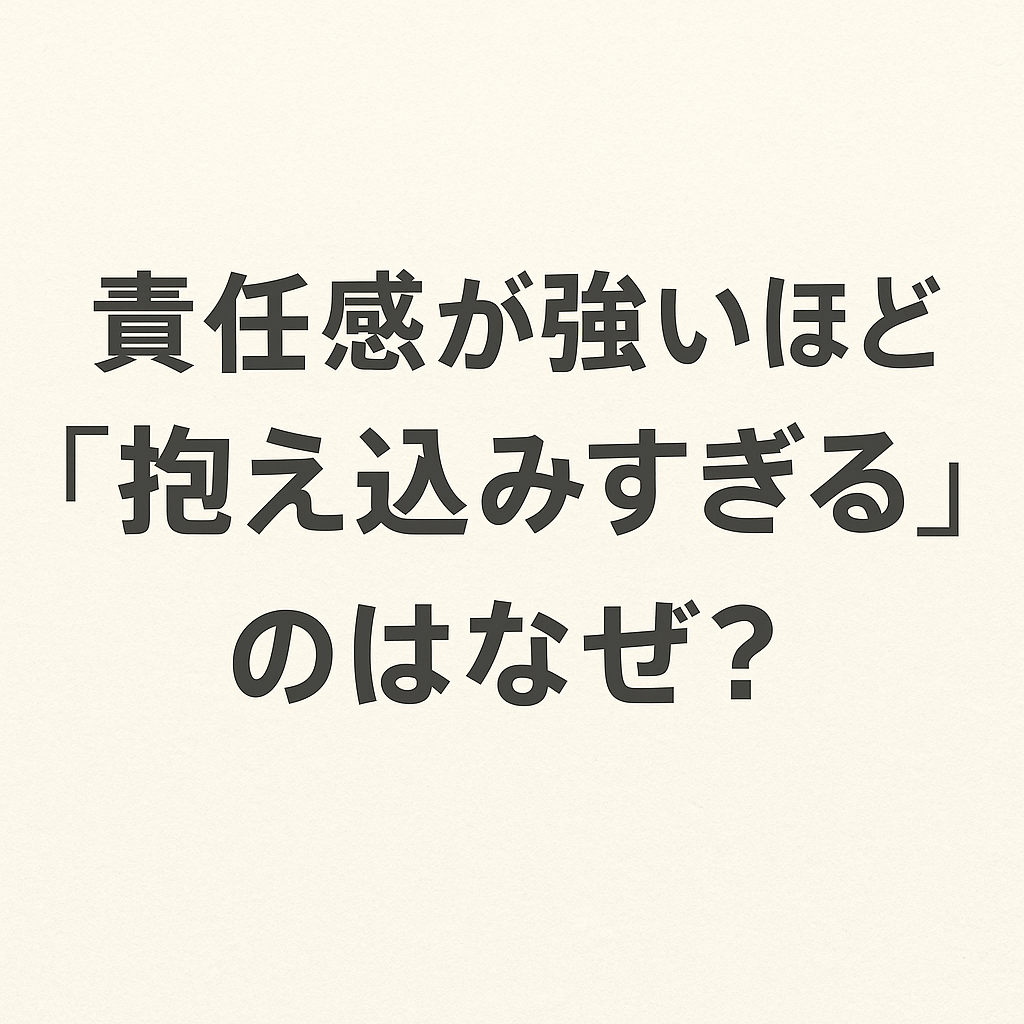
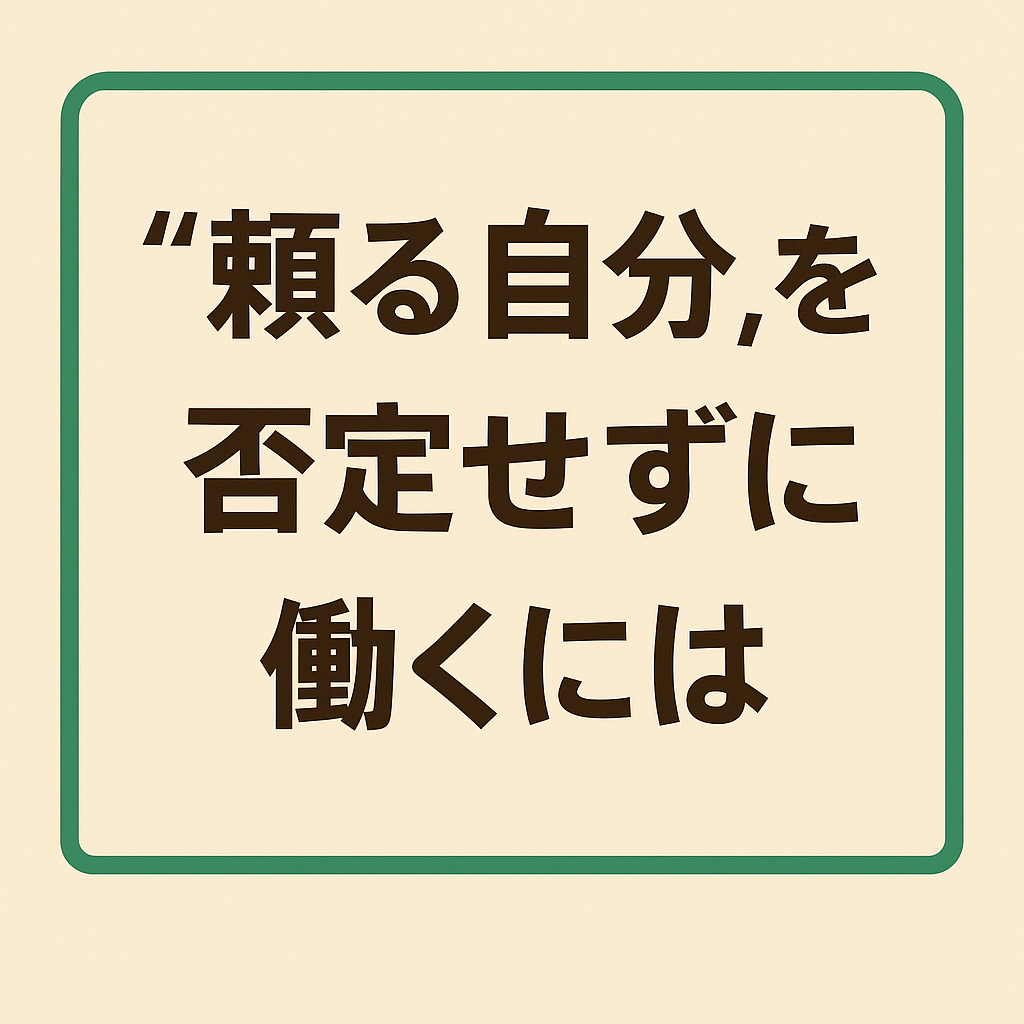
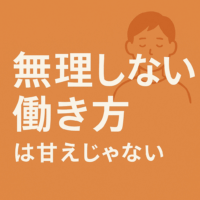
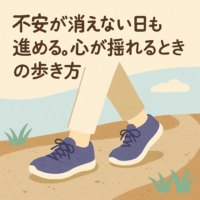
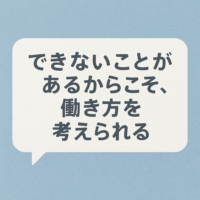
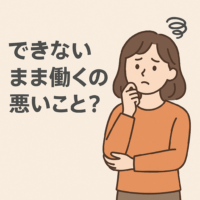

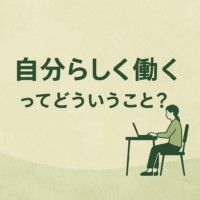
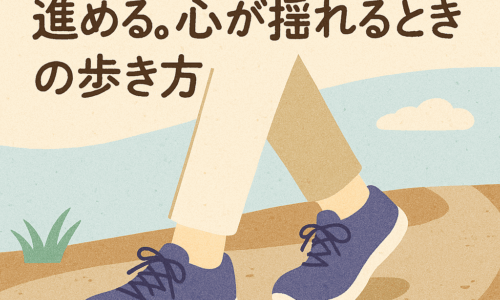
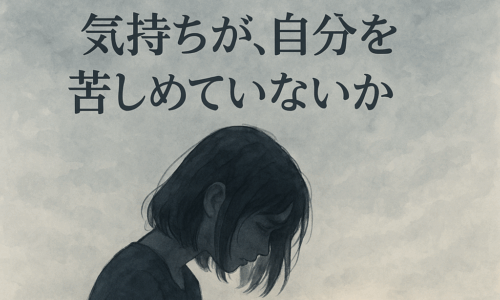
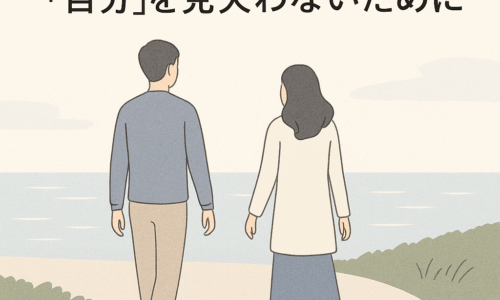
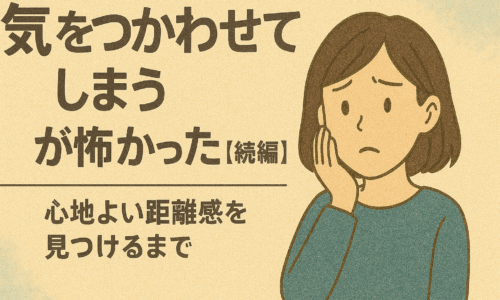
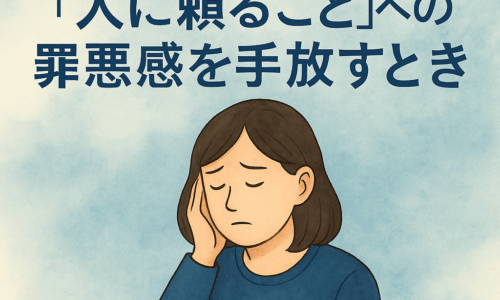
この記事へのコメントはありません。