こんにちは!今日は「障がい理解」について、福祉に少し関心のある方や、障がいのある方と関わる機会がなかった方にも向けて、やさしく・具体的にお届けします。
電動車椅子で生活する筆者自身の視点から、日常や社会のこと、そして「共に生きる」ヒントをお話しします。
- 障がい=かわいそう?というイメージの誤解
- 障がい理解=専門知識じゃない!
- 家庭や日常でできる障がい理解の実践
- 医学モデルと社会モデルの違いって?
- 障がい理解の先にある社会のカタチ
- まとめ:やさしい興味が社会を変える
障がい=かわいそう?というイメージの誤解
福祉に少し興味を持ち始めた方や、障がい者とあまり接点がなかった方から、「障がい者って、大変そう」「支援が必要な人」という印象をよく聞きます。でも、それだけじゃないんです。
私自身、障がいがあるからといって不幸なわけではありません。たしかに生活にサポートは必要です。でも、美味しいラーメンを楽しんだり、野球を観戦したり、好きな音楽に熱中したりと、豊かな日々を過ごしています。
障がいがあるからできない、ではなく、「どうすればできるか」に注目する視点。それが福祉の醍醐味でもあります。
障がい理解=専門知識じゃない!
「障がい理解」と聞くと、専門的な福祉の知識や資格が必要だと思われがちですが、そんなことはありません。
たとえば、車椅子の人に「お手伝いしましょうか?」と声をかける。子どもに「あれ、勝手に動いてる!?」と聞かれたとき、「電動車椅子っていう便利な乗り物なんだよ」と教えてあげる。
こうした日常の中の小さな行動が、立派な「障がい理解」の一歩になります。
家庭や日常でできる障がい理解の実践
福祉を仕事にするかどうかに関係なく、誰でもできる関わり方があります。
- 障がいのある人と関わった経験をSNSなどでシェアする
- 「なにか困っていることがありますか?」と自然に声をかけてみる
- 地域のバリアフリーマップを見て、まちの環境を知ってみる
障がい者と関わる機会がなかった人でも、「知ろうとすること」「日常の中で意識すること」から始められます。
医学モデルと社会モデルの違いって?
福祉に少し踏み込むとよく出てくる言葉に、「医学モデル」と「社会モデル」があります。
- 医学モデル:障がいは“本人の問題”。治療や訓練で克服すべき
- 社会モデル:障がいは“社会の側にあるバリア”によってつくられる
たとえば、段差があって車椅子で入れない建物。これは障がい者の問題ではなく、社会の側の課題ですよね。こうした考え方が「社会モデル」であり、近年の福祉の考え方の主流になっています。
障がい理解の先にある社会のカタチ
今、福祉の現場では「共生社会」「インクルーシブ」という言葉がよく使われています。誰もが地域で当たり前に暮らせる社会を目指すということです。
そのために必要なのは、特別な技術よりも「知ろうとする気持ち」と「行動する勇気」。
福祉に興味を持ち始めたあなたが、今できる小さな一歩が、誰かの暮らしを変える力になるかもしれません。
まとめ:やさしい興味が社会を変える
障がい理解は、専門家だけのものではありません。知識ゼロでも、完璧でなくても、「興味を持った」「ちょっと知ってみようと思った」というあなたの気持ちが、すでに素晴らしいスタートです。
「違いがあるからこそ、支え合える」
福祉の入口は、そんな気づきから始まります。少しでもこのテーマに触れたあなたが、これから出会う誰かと、もっと自然に関われるようになりますように。
最後まで読んでくれて、ありがとう!

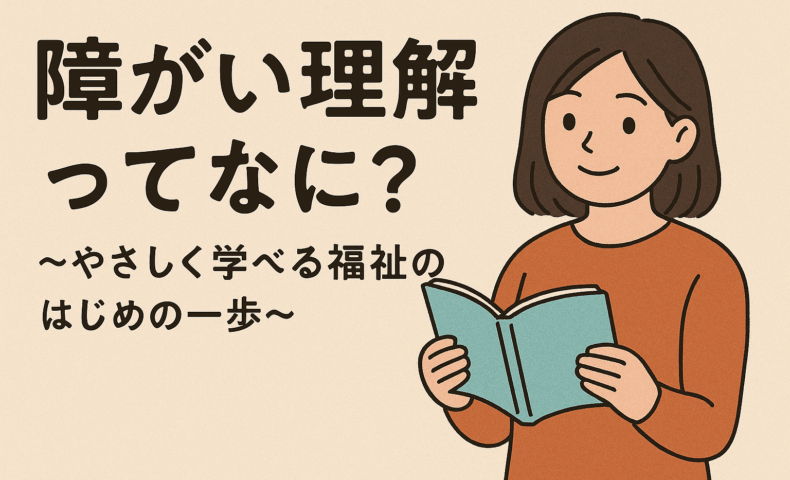


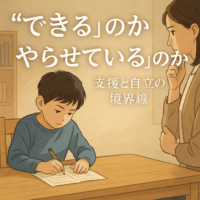


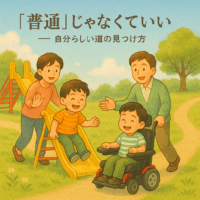

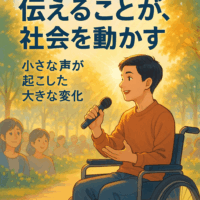

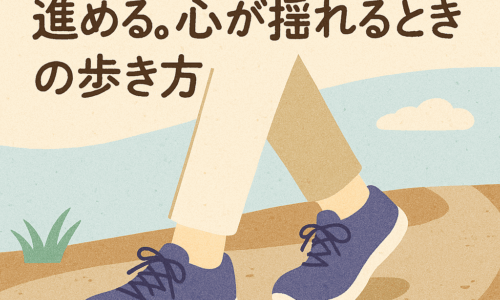
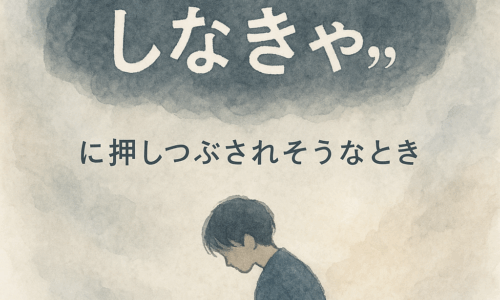
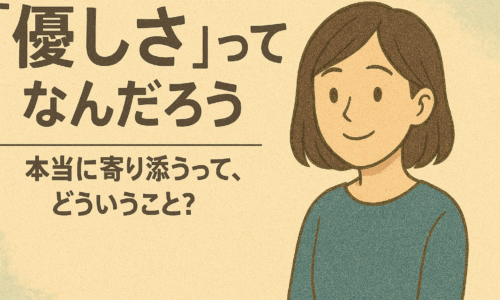
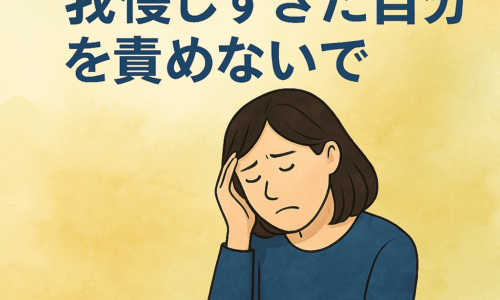
この記事へのコメントはありません。