<p>脳性麻痺の当事者として生きてきた私が、人生の中で何度も出会ってきた“優しさ”。けれどその中には、受け取るたびに胸の奥がちくりと痛む、そんな言葉や行動もありました。この文章では、無意識の偏見や差別が“優しさ”の顔をして現れる瞬間と、それとどう向き合ってきたのかを、いくつかの実体験とともに綴ります。</p><h2>目次</h2>
<ul>
<li><a href=”#intro”>1. はじめに ── 優しさが胸に刺さるときがある</a></li>
<li><a href=”#episode1″>2. 小学部の修学旅行で受け取ったお金</a></li>
<li><a href=”#episode2″>3. 中華料理店で、何度断っても譲られなかった善意</a></li>
<li><a href=”#episode3″>4. お小遣い帳に書かなくていいの?</a></li>
<li><a href=”#labels”>5. 「すごいね」「えらいね」が刺さる理由</a></li>
<li><a href=”#power”>6. やさしさの中にある“支配”という言葉</a></li>
<li><a href=”#growth”>7. 私が“やさしさ”と付き合うようになるまで</a></li>
<li><a href=”#conclusion”>8. まとめ ── 見えない“差別”に名前をつけるために</a></li>
</ul><h2 id=”intro”>1. はじめに ── 優しさが胸に刺さるときがある</h2>
<p>「やさしい人ですね」「思いやりがあるって、すてきだよね」――世の中は、優しさを肯定します。けれど私は、これまでの人生で何度も、“やさしさ”が苦しいと感じた瞬間がありました。ありがたく受け取るべきものとして差し出されたその気持ちが、どうしても私の中では“居場所のないもの”になる。今回はそんな、「やさしさ」という名のグラデーションの中で、私が経験した“苦しさ”と、そこからの気づきを綴ってみようと思います。</p><h2 id=”episode1″>2. 小学部の修学旅行で受け取ったお金</h2>
<p>小学部の修学旅行のとき、ある観光施設で突然知らない大人の女性に「これ、私の気持ちだから」と千円札を渡されたことがありました。先生は「お気持ちだけで…」と返そうとしましたが、女性は「いいんです、これは気持ちだから」と押しつけるように立ち去りました。私は驚きとともに、その場に残ったざらついた感情を覚えています。「ありがたいね」と言われたけれど、「これは私にとっての“やさしさ”じゃなかった」と感じていました。</p><h2 id=”episode2″>3. 中華料理店で、何度断っても譲られなかった善意</h2>
<p>社会人になって中華料理店で一人で食事をしていたとき、ホールの男性が「あちらの方から、これをお渡しするように言われまして…」と現金を差し出してきました。私は何度も断りましたが、その女性は受け取るよう頑なに譲りませんでした。顔には「これは善意なのだから、あなたは受け取るべきだ」という確信が浮かんでいて、私は悔しさを感じました。彼女に悪気はなかったとしても、私の背景や人生を何も知らないまま「かわいそう」と思われたことが、何よりも苦しかったのです。</p><h2 id=”episode3″>4. お小遣い帳に書かなくていいの?</h2>
<p>ある日、和菓子屋さんで商品を買ってレジを済ませたときのこと。店員さんがにこやかに「お小遣い帳に書かなくていいの?」と言いました。一瞬、耳を疑いました。「障害がある人は子ども扱いされる」という思い込みがそこにあったのだと思います。あの一言が私に教えてくれたのは、「自立して生活しているつもりでも、“そう見られていない”ことがある」という現実でした。</p><h2 id=”labels”>5. 「すごいね」「えらいね」が刺さる理由</h2>
<p>「すごいね」「えらいね」「頑張ってて感動した」――これらの言葉も、悪気のないものばかりです。でも私にとっては、時に苦しさを伴います。たとえば、コンビニで「ちゃんとひとりで来れて偉いね」と言われたとき、日常の一コマが“驚くべき出来事”に変換されてしまう。そのギャップが、「自分は普通ではない」と突きつけてくるようでした。</p><h2 id=”power”>6. やさしさの中にある“支配”という言葉</h2>
<p>「助けてあげたい」「あなたのために言っている」――その気持ちが、いつのまにか“支配”に変わっていくことがあります。「こうすべき」「こっちのほうがいい」と、相手の意思を置き去りにする善意。やさしさが“下の立場”を生み出してしまう瞬間です。支援されることと支配されることは違う。私たちは“対等であるための橋”としてのやさしさを求めています。</p><h2 id=”growth”>7. 私が“やさしさ”と付き合うようになるまで</h2>
<p>昔、私は“やさしさ”が怖かったです。何かをしてもらったとき、素直に「ありがとう」と言えない自分を責めました。でも今は少しずつ付き合えるようになってきました。大切なのは「私の意思が、そこにあるかどうか」。聞いてくれるやさしさ、寄り添うやさしさは、私の中にも自然に受け止められるようになりました。</p><h2 id=”conclusion”>8. まとめ ── 見えない“差別”に名前をつけるために</h2>
<p>差別にはあからさまなものだけでなく、“やさしさ”の皮をかぶったものもあります。必要なのは「同情」ではなく「理解」。やさしさを“相手を下に置く手段”ではなく、“対等であるための手段”にできる人がもっと増えてほしい。私のように、「ありがとう」より「どうして?」が先に浮かんだ経験のある人もいる。やさしさが本当にやさしさとして届く社会にするために、私はこれからも伝えていきたいのです。</p>
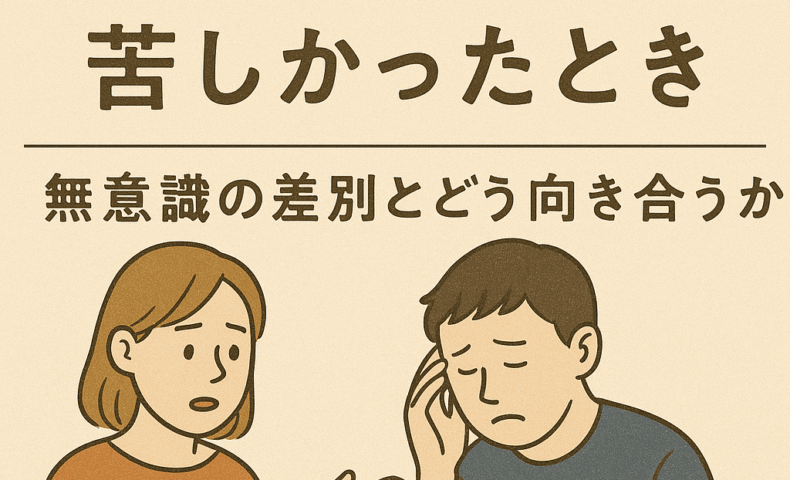

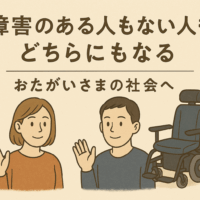
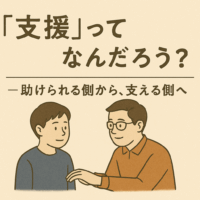


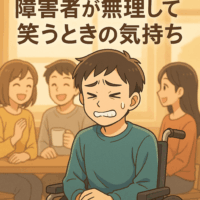


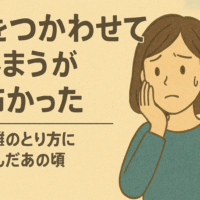


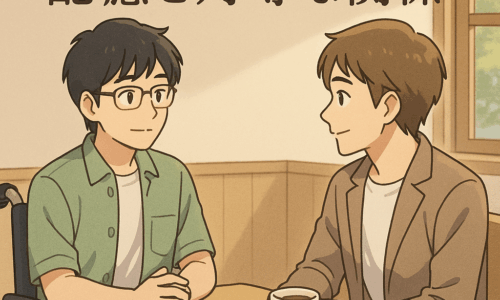
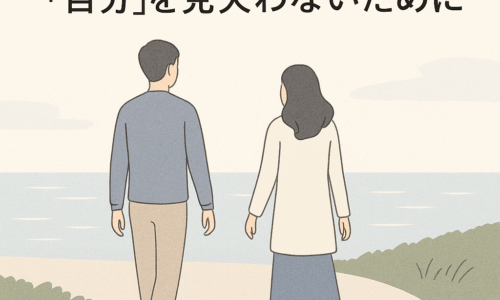

この記事へのコメントはありません。