私たちは日常の中で、無意識のうちに「人に合わせすぎてしまう」ことがあります。
例えば、会話の中で相手に合わせてうなずき続けたり、本当は違う意見を持っているのに空気を壊したくなくて黙ってしまったり…。一見すると小さなことですが、積み重なると「自分が何を感じているのか」「本当はどうしたいのか」が分からなくなり、心がどんどん疲れていくのです。
私自身、この「合わせすぎてしまう」傾向がとても強いと感じています。特に障害があると、日常的に人の助けが必要な場面が多くなります。支援を受ける立場だからこそ、「嫌われたらどうしよう」「見放されたら助けてもらえないかもしれない」という恐怖感が常に心の奥にあります。だから、相手に嫌われないように、なるべく相手の意向に合わせようとしてしまうのです。
でも、それを繰り返しているうちに、自分の本当の気持ちが分からなくなることがあります。
「私はどうしたいんだろう?」
「これって本当に自分の望みなのかな? それともただ相手に合わせただけなのかな?」
そんな疑問が積み重なり、気づけば“自分がいない感覚”に襲われてしまうのです。
「合わせる」ことは悪いことではない
ここで大事なのは、人に合わせること自体が決して悪いわけではないということです。
人に合わせることは、相手を思いやる気持ちの表れでもあり、円滑な人間関係を築くために必要な力でもあります。協調性は、社会で生きていくうえで欠かせないものです。
ただ問題は、それが「自分を押し殺すこと」とイコールになってしまうときです。
自分を犠牲にしてまで相手に合わせ続けると、心は少しずつ疲弊していきます。やがて「自分が何をしたいのか分からない」「ただ相手に合わせるために生きている」と感じるようになるのです。これは、誰にとってもつらいことです。
「合わせすぎてしまう自分」に気づけたら、それは前進
私が大切にしているのは、「合わせすぎてしまう自分」に気づくことです。
気づけないまま過ごしていると、ただ漠然とした疲れやストレスだけが積み重なっていきます。でも、「あ、また自分を押し殺してしまったな」と振り返ることができると、それは次への一歩になります。
私はその気づきを残すために、毎日手帳に「今日言えたこと」と「言えなかったこと」を書き留めています。
たとえば、
・会議で本当は違う意見があったけれど黙ってしまった
・友人に頼まれたことを断れなかった
・逆に、小さなことだけれど「それは難しい」と伝えられた
といった出来事を具体的に記録します。
書き出してみると、自分のパターンが見えてきます。「私はこういう場面では我慢してしまうんだな」と分かると、次はそこに小さな挑戦を加えることができるのです。
事例:小さな実践から始めてみる
私はあるときから「一度に全部を変えようとしない」と決めました。
例えば、頼まれごとをされたときに「いいよ」と即答してしまうのではなく、「少し考えてから返事するね」と言うようにしました。たった一言ですが、このワンクッションを置くだけで、相手に合わせすぎる自分を少しずつ手放せるようになったのです。
また、支援を受ける場面でも、「今日はこうしてほしい」と小さな希望を伝える練習をしました。相手にすべてを委ねるのではなく、自分の意思をほんの少しだけ表すこと。それを繰り返すことで、「私はこうしたい」という感覚を取り戻せるようになってきました。
「自分を大切にする」ことと「人を大切にする」ことは両立できる
人に合わせすぎる自分を変えたいと思うとき、つい「もっと自分勝手にならなきゃ」と考えてしまう人もいるかもしれません。でも、そうではないのです。
大切なのは、自分と相手の両方を尊重することです。
相手に合わせすぎて自分を苦しめる必要はありませんし、かといって相手を無視して自分だけを押し通す必要もありません。その間のバランスを探していくことこそが、「自分らしく生きる」ということではないでしょうか。
まとめ
人に合わせすぎてしまうのは、優しさや不安の裏返しでもあります。
特に、支援を受けて生きる障害者にとっては「嫌われたら困る」という切実な思いから、合わせすぎるクセが強くなることもあります。けれど、その中でも「本当はどうしたいのか」を少しずつ確かめていくことは可能です。
気づいたときに立ち止まり、小さな練習を繰り返すこと。
その積み重ねが「自分を見失わないこと」につながっていきます。
人に合わせる優しさを持ちながら、自分の声にも耳を傾けていく。
その両立を目指すことが、私たちの生き方の希望になるのではないでしょうか。


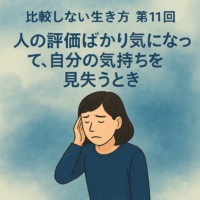
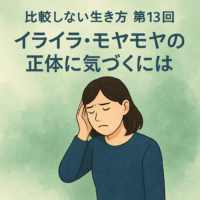
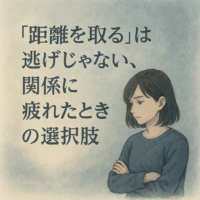
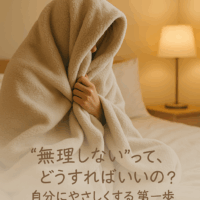
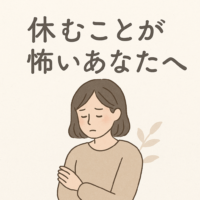
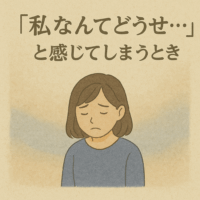

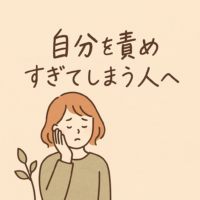

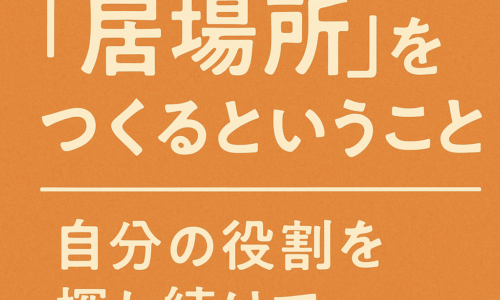
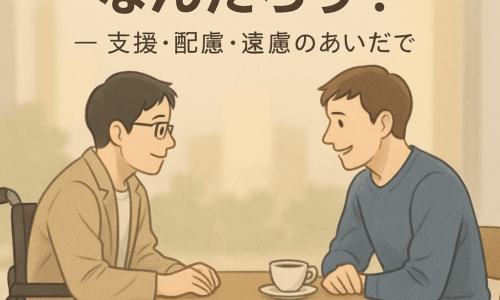
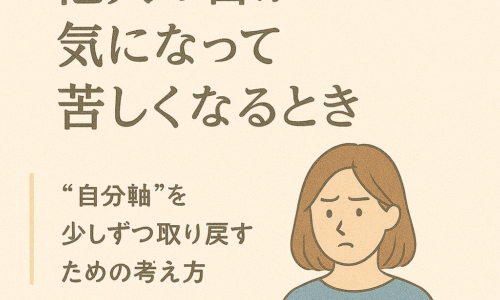
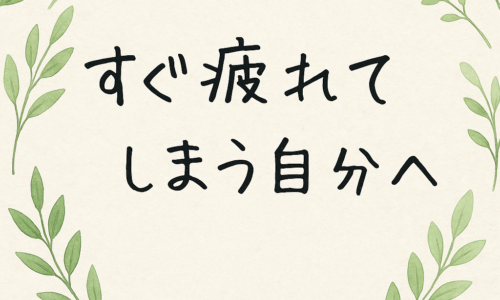
この記事へのコメントはありません。